第4回
脱炭素への対応が勝ち残りの道、事業構造の転換に本気に取り組むとき
イノベーションズアイ編集局 経済ジャーナリストM
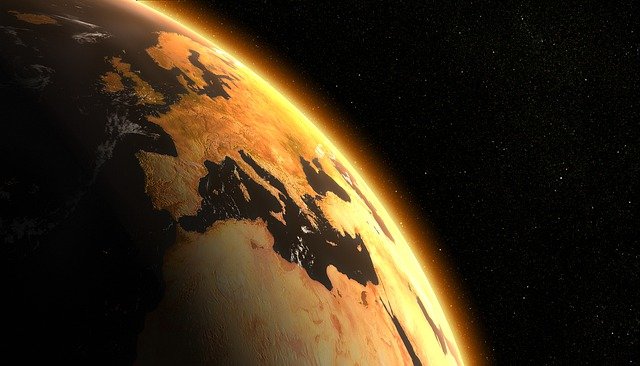
地球温暖化という人類にとって深刻な危機が迫る中、各国は本気になって脱炭素に取り組むべきときだ。企業も環境意識を高める市民の声に応えられなければ支持を得られず、市場からの退出を余儀なくされる。言い換えると国にとって産業構造の転換、企業にとって事業再編の好機だ。生かさない手はない。
「100年に一度の大変革期」を迎えた自動車産業が典型例だ。排ガスを出さないゼロエミッションの流れは加速、ガソリン車から電気自動車(EV)など電動車へのシフトが間違いなく進む。対応できないメーカーは脱落するしかないサバイバルレースが始まったわけだ。各社がEVシフトを加速するのは脱炭素に向けた環境規制の高まりがある。欧州連合(EU)の欧州委員会は7月、35年に域内の新車が排出するCO2をゼロにすることを義務付ける規制案を発表した。中国も35年までに、新車販売の全てをEVなど新エネルギー車やハイブリッド車にする計画だ。
「火力発電が大部分を占める日本ではEVを増やしても脱炭素になりにくい」と指摘する声がある。しかし日本メーカーもEV化にかじを切るしかない。高性能ガソリン車を発売しても売れなくなるからだ。また部品点数が多いガソリン車からEVへのシフトは失業者を生みかねないといって、国内の車部品メーカーで働く約70万人の「雇用を守る」と強調するメーカーもある。そのためにEVシフトを遅らせることは今の時点では正しい選択かもしれないが、やがてガソリン車は売れなくなる。今の雇用を守っても5~10年先の雇用は守れない。いつの雇用を守るのかが問われる。
産業構造の転換にいち早く対応する企業が勝ち残るのは自明の理だ。ある日本メーカー幹部は「技術者としてガソリン車を残したいが、社会が変わった。経営判断としてEV化を加速する」と話した。もはや立ち止まることは許されない。自動車産業に限らず、COP26を機に、日本企業は産業構造の転換に向けた競争を迫られるのは確かだ。
- 第50回 ブルーカラーはカッコいい AIに奪われない仕事として評価高まる
- 第49回 スーツでおもてなしの心を示す
- 第48回 社員への感謝の言葉でエンゲージメントは向上する
- 第47回 強い横綱と真っ向勝負の新鋭がぶつかり合う相撲は面白い ~新旧交代、新陳代謝こそが成長をもたらす~
- 第46回 脳の健康状態を知って認知症を予防
- 第45回 「まぜこせでええやんか」 マイノリティー集団が多様性社会を訴える ~一般社団Get in touchが舞台公演~
- 第44回 窮屈な日本 いつまで我慢できるの? デンマーク人ビジネス人類学者が提唱するリーダー像
- 第43回 日本原電、東海第二の再稼働に向け安全対策進む 「念には念を入れて」の姿勢貫く
- 第42回 道徳・倫理観を身につけている?
- 第41回 民法906条? 日本一美しい条文、相続問題は話し合って決める
- 第40回 「褒める」「叱る」で人は伸びる
- 第39回 危機管理の本質を学べる実践指南書 社員は品性を磨き、トップに直言する覚悟を
- 第38回 円より縁 地域通貨が絆を深める
- 第37回 相撲界を見習い、産業の新陳代謝で経済活性化を
- 第36回 広報力を鍛える。危機への備えは万全か
- 第35回 水素社会目指す山梨県
- 第34回 「変わる日本」の前兆か 34年ぶり株価、17年ぶり利上げ
- 第33回 従業員の働きがいなくして企業成長なし
- 第32回 争族をなくし笑顔相続のためにエンディングノートを
- 第31回 シニアの活用で生産性向上
- 第30回 自虐経済から脱却を スポーツ界を見習え
- 第29回 伝統と革新で100年企業目指せ
- 第28回 ストレスに克つ(下) 失敗を恐れず挑戦してこそ評価を高められる
- 第27回 ストレスに克つ(上) ポジティブ思考で逆境を乗り切る
- 第26回 ガバナンスの改善はどっち? 株主はアクティビスト支持 フジテックの株主総会、創業家が惨敗
- 第25回 やんちゃな人を育ててこそイノベーションが起きる 「昭和」の成功体験を捨て成長実感を求める若手に応える
- 第24回 人材確保に欠かせない外国労働者が長く働ける道を開け 貴重な戦力に「選ばれる国・企業」へ
- 第23回 人手不足の今こそ「人を生かす」経営が求められる 成長産業への労働移転で日本経済を再生
- 第22回 賃上げや住宅支援など子供を育てやすい環境整備を 人口減少に歯止めをかけ経済成長へ
- 第21回 賃上げで経済成長の好循環をつくる好機 優秀人材の確保で企業収益力は上昇
- 第20回 稼ぎ方を忘れた株式会社ニッポン 技術力で唯一無二の存在を生かして価格優位をつくり出せ
- 第19回 稼ぐ力を付けろ 人材流動化し起業に挑む文化創出を
- 第18回 リスクを取らなければ成長しない。政府・日銀は機動的な金融政策を
- 第17回 企業は稼いだお金を設備と人への投資に回せ 競争力を高め持続的成長へ
- 第16回 インパクト・スタートアップが日本再興の起爆剤 利益と社会課題解決を両立
- 第15回 適材適所から適所適材への転換を ヒトを生かす経営
- 第14回 日本経済の再興には「人をつくる」しかない 人材投資で産業競争力を強化
- 第13回 「Z世代」を取り込むことで勝機を見いだす
- 第12回 改革にチャレンジした企業が生き残る
- 第11回 「型を持って型を破る」 沈滞する日本を救う切り札
- 第10回 ベンチャー育成、先輩経営者がメンタリングで支援 出る杭を打つことで日本経済に刺激
- 第9回 コロナ禍で鎖国の日本 外国人材に「選ばれる」仕組づくりを
- 第8回 「御社の志は何ですか」社会が必要とする会社しか生き残れない
- 第7回 大企業病を患うな 風通しのよい組織を、思い込みは危険
- 第6回 常識を疑え、ニーズに応えるな ベンチャー成功のキラースキル
- 第5回 トップを目指すなら群れるな 統率力と変革の気概を磨け
- 第4回 脱炭素への対応が勝ち残りの道、事業構造の転換に本気に取り組むとき
- 第3回 東芝VSソニー 複合経営は是か非か 稼ぐ力をつけることこそ肝要
- 第2回 トップは最大の広報マン、危機管理の欠如は致命傷
- 第1回 リーダーに求められるのは発進力 強い意志と覚悟で危機に挑む

















