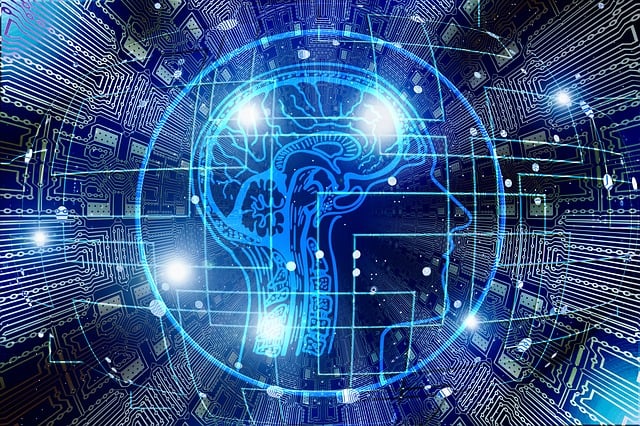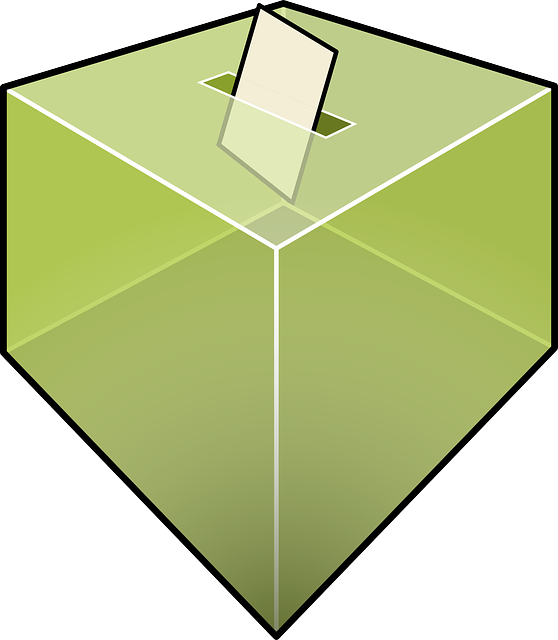コロナ後の世界
筆者:イノベーションズアイ編集局 経済ジャーナリストA

新型コロナウイルスの感染拡大が、世界の経済社会に大きな影響を及ぼしています。生活スタイルや働き方は大きく変化し、先行きを見通すことも非常に難しくなっています。ただ、コロナ禍以前から起きていた変化、例えば人口減少やグローバル化、デジタル化といった動きや脱炭素をはじめとする環境対策などがより進んでいく、ということは間違いなさそうです。しかし、そうした変化の中で何をするのかをみつけだすのは容易ではありません。だからといって、そのままにしておくわけにもいかない。本稿は、そんなコロナ後の経済社会を乗り切るための試行錯誤をテーマとし、随所で繰り広げられる取り組みや現象について、思い付きや独断と偏見で言及するものです。
-
静岡市中心街の西側に安倍川という大きな川がある。この川は、普段はそれほど水の多いわけではない。が、江戸時代には安全保障上の配慮から橋がなかったため、対岸との往来は渡し船や川渡し人足に頼っていた。筆者は、江戸時代後期の戯作者で絵師でもある十返舎一九の“生誕の地”の近所に住んでいるのだが、その十返舎一九の著作「東海道中膝栗毛」には安倍川の渡しが「川ごしの 肩車にて われわれを ふかいところへ ひきまはしたり」という感じで登場する。

-
1年半前はまだ新型コロナウイルス禍もあり、マスクが欠かせなかった。静岡は地方都市にしてはすばらしく発展しているが、シャッターの閉まっている商店も多く、地方都市の厳しい現実をみたような気にもなった。

-
2月22日は「にゃんにゃんにゃん」ということで「猫の日」だった。近所(静岡県内)のスーパーなどではキャットフードの特売イベントが行われていたし、地元のテレビやラジオでも猫にちなんだ商品やサービスの紹介、猫に関する話題が多かった。

-
観光庁が1月17日に発表した2023年10~12月の日本での外国人旅行者の消費額は1兆6688億円、この結果、2023年通年では5兆2923億円となり、ともに過去最高を更新した。通年の消費額は新型コロナウイルス禍前の2019年比で9.9%増となっている。同日、日本政府観光局(JNTO)が発表した2023年の訪日観光客数は2506万人6100人で前年比6.5倍、2019年の8割程度まで回復している。円安などの強い追い風もあるが、この分野に限ればかなり順調にコロナ禍から回復したことになる。

-
デジタル化がどれだけ進んでも、やはり情報を伝えるのは難しい。“伝えられる側が特に興味を示していないが重要な情報”である場合は特にそうだ。

-
いよいよ年末だ。来年の予定もちらほら入り始めている。そこで来年の手帳が必要なのだが、いまのところない。

-
新型コロナウイルス渦からの回復基調が鮮明になってきた。筆者が住む静岡市も人流が大幅に回復し、週末などは市中も大勢の人でにぎわう。東京方面に帰省しようにも新幹線が思うように予約できないほど。感覚的にはもう元通りだ。

-
新型コロナウイルス禍前だったと思う。先輩がこんなことを言っていた。
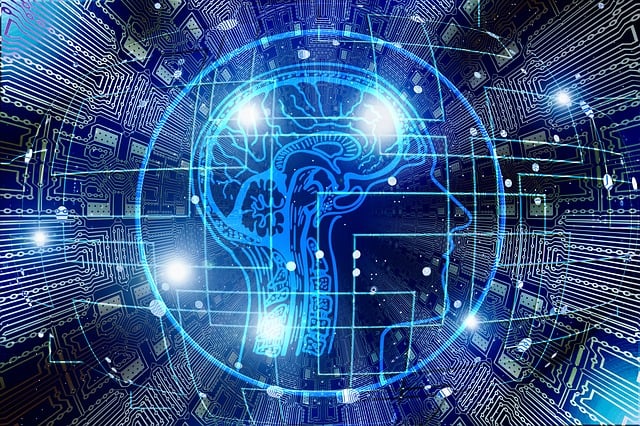
-
自分の行動からも、新型コロナウイルス禍はデジタル化を加速したと思う。

-
中国のバブル崩壊が取りざたされている。以前から景気後退が予想されてはいたし、不動産大手である中国恒大の経営危機は2年前からダラダラ続いた。不動産大手の遠洋集団もデフォルトが懸念されているとの報道がある。日本のバブル崩壊もそうだったが、こういうものはへんにネバると重篤化するだけに、いよいよの時が心配だ。

-
SNSがビジネスに活用されるようになって久しい。いわゆる口コミの電子版といった形で、商品やサービスの宣伝・告知に大きな威力を発揮している。

-
人口減少は困ったことである。学校や病院が維持できなくなったり、新たなインフラ整備が難しくなってきた。

-
マイナンバーカードに関連するトラブルが続いている。地方自治体などによれば、5月からは一連のトラブルに起因するとみられるカードの返納も増えているとか。行政のデジタル化が強く求められる中で、どうにも困ったことだ。

-
リニア中央新幹線の工事が、最大の難所である静岡工区で“難航”している。静岡工区は南アルプスの地下を通るトンネル工事だ。リニアが静岡県を通るのはこのトンネルのあたりだけで、県内に駅などができるわけではない。

-
新型コロナウイルス禍でデジタル化は大いに進んだ。地方の市役所でも“書かない窓口”を導入し、各種行政手続きを効率化することで窓口の混雑を解消する試みが行われ、それなりに成果も出ているとか。マイナンバーカードはトラブルが続いているが、これも問題点が解決できれば行政手続きも効率化が進むことだろう。

-
さまざまな経済指標や統計数字も新型コロナウイルス禍が終焉し、アフターコロナの段階に入ったことを示している。

-
いよいよ新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが季節性インフルエンザと同じ5類になった。

-
都道府県の知事や議員、市町村の首長や議員を選ぶ統一地方選挙が終わった。統一選は4年に一度だが、いろいろな事情で選挙の時期がズレることも多い。とはいえ、今回も全国で約1000もの選挙が実施された。
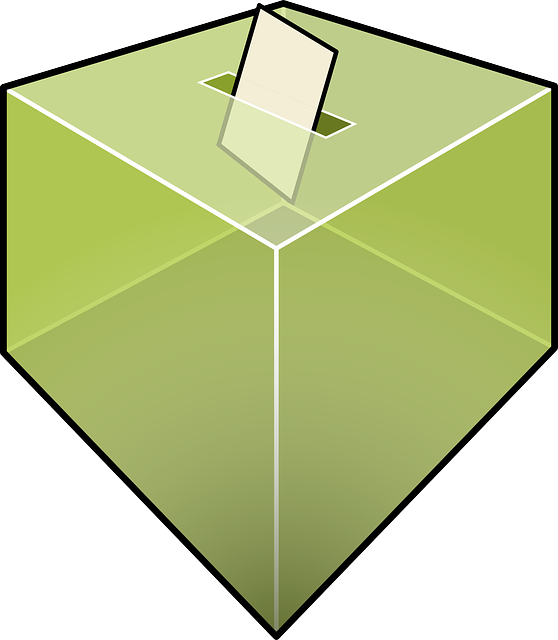
-
日本のようなスーパー高齢社会でインフレがいいのかどうかには議論があるものの、海外の状況などを踏まえると、ここで賃上げを何とかしなければ国力の面での先行き不安だ。

-
福井県鯖江市はメガネフレーム生産で国内の9割以上ものシェアを有している。新潟県燕市はスプーンやフォークなど金属洋食器生産で同9割ともいわれる。

-
3年間に渡った新型コロナウイルス禍だが、ゴールデンウィーク明けには感染症法上の位置づけも変わり、季節性インフルエンザと同様の扱いになる。

-
コロナ禍からの再起動もいよいよ本番といった感じになってきた。経済指標などをみると、コロナ禍の過去3年からは着実に復興しており、今年はコロナ前の2019年比でどうか、というところまできている。

-
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の分類を、ジフテリアやコレラと同等の2類相当から、季節性インフルエンザと同じ5類に変更することが決まった。新型コロナウイルスには、正確には新型インフルエンザ等に対応するための特別措置法が適用されてきたが、ゴールデンウィーク明けからは5類。冬場に流行るインフルエンザと同じ扱いになる。

-
モノからコトへというが、サービスもそれほどは売れない。GDP(国内総生産)の約半分強を占めるのは個人消費だが、その減少傾向が顕著だ。人口が減少しているわけで仕方ない面もある。が、こうした傾向に拍車をかけている要因もある。

-
景気の先行き不透明感が一層増している。とはいえ、まだ具体的な動きはみえていない。そういう意味では、先行きが良くないというマインドが強まりつつある、という感じだろうか。12月14日に日銀が発表した企業短期経済観測調査、いわゆる“日銀短観”によれば、全国の全産業のDIは6で、9月の前回調査より3ポイント上昇。前回時点の12月の予想より5ポイントも高い結果となった。

-
まだ来て2か月だが、ここはつくづく温暖なところだと感じる。東京と行き来する度に思うが、12月初旬段階では5度程度は暖かい。水もいい。食べ物は海産物を中心に新鮮な上に安価だ。そしてなにより、いつも大きな富士山が見える。

-
財務省によると、国債と借入金、政府短期証券を合計した国の借金は2022年の9月末時点で1251兆3796億円だったという。これは、1年前より36兆2264億円の増加で、9月末として過去最大である。

-
最近、テレビやラジオで“ユーミン”こと松任谷由実さんの特集がよく組まれている。それもそのはず。なんと、今年はデビュー50周年なんだという。そんなことも知らなかったのか、と言われそうな話だ。とはいえ、昭和40(1965)年生まれの筆者はユーミンを人並みには知っている。

-
ロシアのウクライナ侵攻に伴う世界的な原油高や穀物高が続く中で、一人負けのような円安に襲われている。円高に振るもための手立ても事実上ない。日本銀行による為替介入も、米国をはじめとする“相手国”に協調して是正する意志がない以上限定的だ。 新型コロナウイルス禍からの“復興期”だけに、みんな自国のことに一生懸命だ。そもそも、こういうときだけに通貨安のメリットはあまりない。
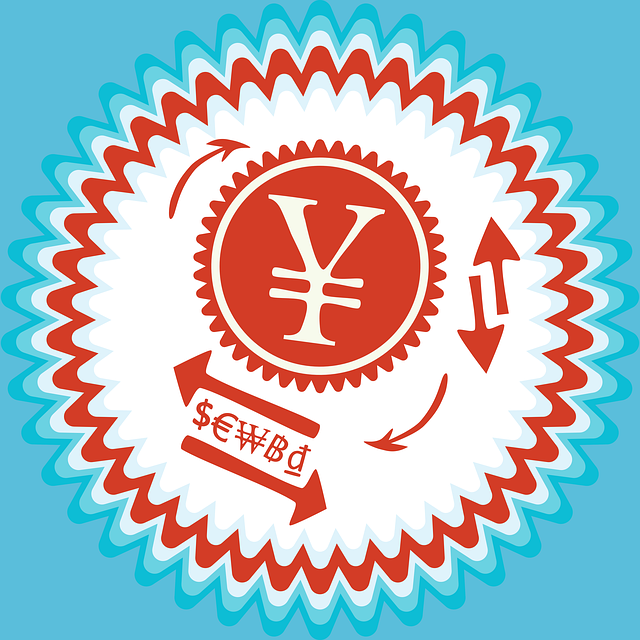
-
2022年8月の有効求人倍率が1.32倍にまで改善したという。上昇局面としては2016年上期の水準と同等だ。人手不足は慢性的な感じもするが、数値で見る限り景気が回復しているという気になってしまう。

-
新型コロナウイルス禍は収束に向かいつつある。日本でも感染者の全数把握を見直すことで、いよいよ経済社会はコロナ後の復興にむけて本格始動する格好だ。
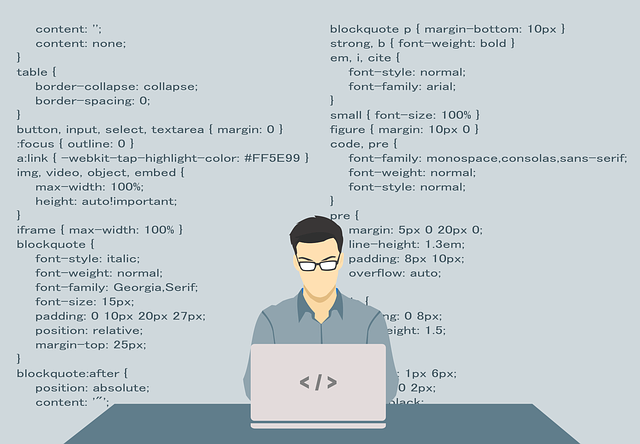
-
京セラ創業者である稲盛和夫氏の死去を悼む声が世界中に広がっている。京セラを一代で世界的な電機メーカーを育て上げた経営手腕、それを支えた「稲盛哲学」と呼ばれる考え方は、世界中の経営者から注目されてきた。訃報は国内外の報道機関から破格の大ニュースとして扱われ、国内の新聞各紙も評伝その他の記事を数ページにわたって掲載。その死を惜しんだ。

-
2022年8月中旬。新型コロナウイルスの感染者は国内も全世界も過去最多で推移している。しかし、今夏は国内でも行動制限なしということで、いつもの夏が戻ってきた感じだ。とはいえ、やはり2年以上にも渡った断続的な行動制限や日常のコロナ対策は染みついていると感じる。

-
新型コロナウイルスの感染者が増えている。いわゆる第7波だ。3年ぶりの行動制限なしで夏休みを迎えつつあるだけに、この第7波の影響がどう出るのかが心配される。
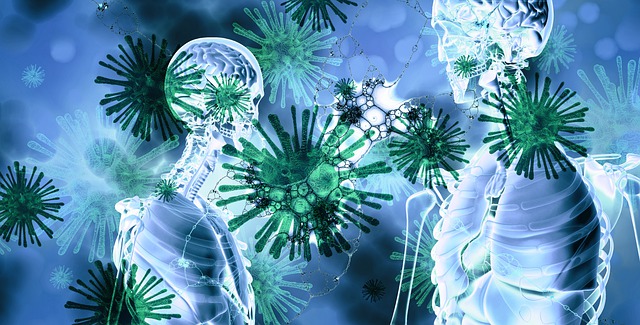
-
最近、「事業再構築補助金を活用してこの事業を始めた」という話をよく聞く。新型コロナウイルス禍で壊滅的な打撃を受けた居酒屋がスイーツ製造事業で復活したり、旅行会社が教育事業に参入したり…

-
食品の値上げが相次いでいる。中でも小麦や油脂類の価格上昇が目立つ。こうした値上げは世界中で起きているが、日本は食糧やエネルギー資源の大半を輸入に頼っているだけに深刻度は高い。まずいことに、円安も進んでいる。改めて思うが、日本はこういう事態に相変わらず弱い。しかも、近年はそういう構造上の欠点を補おうという議論も少ない。多いのは“金をくれ”みたいな話ばかり。

-
新型コロナウイルス禍が起きる前までは、本(書籍)の販売は右肩下がりが続いた。電子書籍を加えた書籍全体でも減少傾向は変わりない。人口が減っているわけで、一人当たりの読書量が増えでもしなければ減少も仕方ない。その一人当たりの読書量もどうやら減っている。
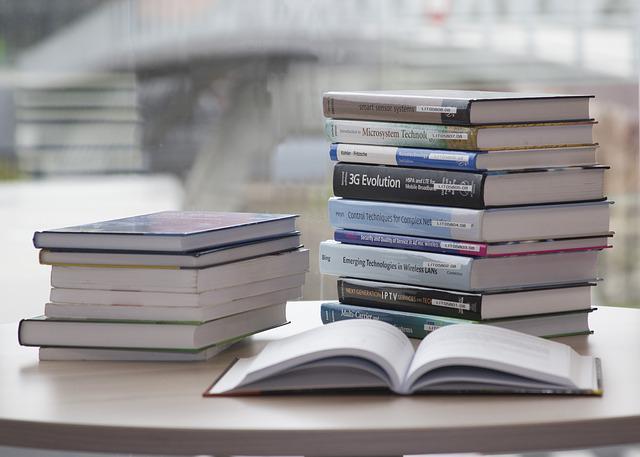
-
それにしても、資源や食糧が高いというのはこまった話である。世界の経済はここ2年以上も新型コロナウイルス禍で“休止状態”だった。いよいよ再稼働だ!という矢先にこれじゃ経済復興も思うように進まない。高いことに加え、供給自体に問題があるモノも多い。たとえば半導体だ。半導体の供給不足で、スマホやパソコンのような情報機器はもとより、自動車や家電製品の生産も思うように進まない。
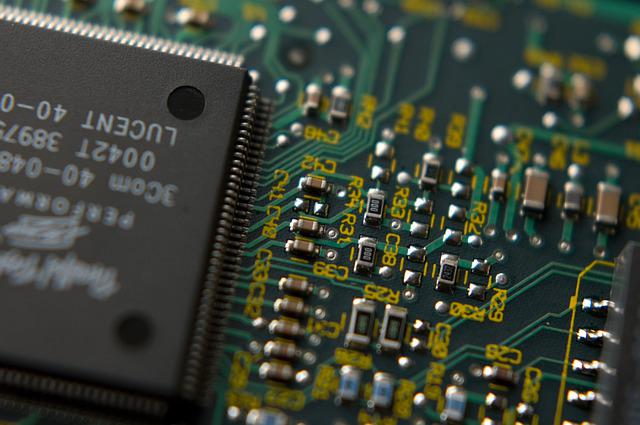
-
デジタル化、いわゆるデジタルトランスフォーメーション(DX)を進めよう!というようなことが言われるようになって久しい。思い起こせばいろいろと名前も変わってきたもんだ。インターネットの活用や携帯電話・スマートフォンの普及など、はかばかしく進んだものもある。新型コロナウイルス禍はこうした流れを加速した感がある。たとえばキャッシュレス化であるとか、通信販売やオンライン会議、電子認証なども日常的になってきた。
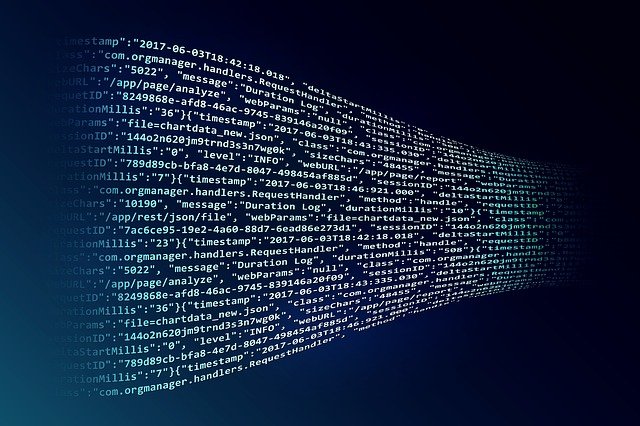
-
新型コロナ禍に続くロシアのウクライナ侵攻で原油の歴史的な高値が続いている。米ニューヨークで取引されるテキサス州西部を中心とした地域で産出される原油の先物、いわゆるWTI原油価格は3月以降コンスタントに1バレルあたり100ドルを上回る水準が続く。こうした価格の推移は原油に限ったものではない。金属や小麦粉などさまざまなものが程度の差こそあれ高騰している。

-
2022年3月に発表された有効求人倍率は1.20倍。前月比0.03ポイントの上昇ということで上昇傾向にはあるものの、思ったほどではないという印象だ。もっと上昇するかと想像していた。まん延防止等重点措置の全面解除などで新型コロナウイルス禍の収束期待が高まっているとはいえ、様子見が続いているということだろうか。

-
デジタルと何かの融合で何かが始まる。イノベーションは知と知の結合で生まれる“結合知”である。通販や事務処理を自動化することがDXだと思ってはいけない。どうせ誰にもわからないのだから、わからない前提でいろいろと挑戦することが重要だと感じる。

-
パワハラ防止措置が、組織内のコミュニケーションを阻害し、個々の信頼関係の希薄化に拍車をかけないことを願いたい。

-
共感や理解に基づいた言葉が多用されているという。共感とは感情の共有だ。デジタル時代だからこそ、感情をしっかり伝え合う必要が出てきている、ということらしい。

-
へんなマスコミの報道に振り回されず、へんな思い込みにとらわれず、いまこそ想像力を働かせよう

-
はやく気兼ねなく会食や飲み会ができる日々がこないものか。もちろん、そこに知を持ち寄り、イノベーションを巻き起こしたいからだ。ということにしておこう。まあ、そういう日常があったコロナ前もイノベーションは起きていないような気はするのだが…