第77回
生成AIを活用しながら人間力を発揮する
StrateCutions (ストラテキューションズ)グループ 落藤 伸夫

すさまじいスピードで進化する生成AIを使いこなせるか否かが、これからのビジネスを渡り歩くポイントになりそうです。一方で、生成AIの使い手になれば安泰か。たぶん、それだけでは足りないでしょう。人間力も求められます。今回は、この点について考えていきます。
生成AIという有能な「思考の壁打ち相手」
以前は「有能な専門職」をどれだけ抱えているかが強みであり他との差別化要因とされていましたが、生成AIの進歩によりこの構図に変化が生じていると感じられます。
「我が社は生成AIでは対応できない超専門分野に特化しているので、そのような淘汰は生じない。」本当にそうだったらとても喜ばしいことですが、そうは問屋が卸さない可能性が懸念されます。産業革命期を観察すると、人間力にのみ頼るのではなく機械力と組み合わせて、今まで実現できなかったパフォーマンスをあげた者が勝利者になったとうかがえます。
生成AIの強みはインターネット上の莫大な情報をもとに合理的な答えを返してくれることです。「当たり前だ!」その通りですが、実は革新的な出来事です。今までは「世の中に知られていない(常識外れな)考え」について相談する相手を見つけるのは至難の業でした。
広範な知識をベースに適切な返答ができる能力を持ち、なおかつ「そのような常識外れを考えること自体、間違っている」などの反応をすることのない相談相手を得ることは、今までなら先進国元首や超大企業の経営者でもなければ難しかったのです。
生成AIの登場は、そのような相談相手を誰もが無料で手にできることを意味しています。
インプットに留まらずアウトプットまで求められる
生成AIと思考の壁打ちができればこれからの世界を泳いでいけるのか?未来を知ることはできませんが「それだけでは足りない」ことは言い切れます。思考の壁打ちはインプットに過ぎません。アウトプットが必要です。
アウトプットというと「文章を書いて発表すること」をイメージしますが、ビジネスでは「売上・利益に繋がる言動をすること」です。新製品の製造はもちろん、多くのビジネスパーソンなら「上手なセールストークで売上を増やす」や「部下に効率よく働いてもらうマネジメントを行う」などがアウトプットに該当します。
このように考えるとビジネス上のアウトプットとは「自分が何かを生み出すこと」だけでなく「他人に影響を及ぼす」ことも含まれることが分かります。
前者の「何かを生み出すこと」において、いくつかの分野で生成AIが強みを発揮しています。大規模・複雑なプログラム開発において、コマンドを一つ一つ自分で考えて入力するのではなく、実現したい機能を言葉で表現して生成AIに作成してもらう方法が広がっていると聞いています。それで出来上がったプログラムの挙動や成果が期待とは異なっていたら、自分で修正するのではなく、再び言葉で修正を指示するのです。
開発者は、今までは複雑な構成のプログラムでも自力で理路整然と作り上げられることが強みでしたが、今は当該部分は生成AIに任せ、自分はより高い視点でシステムを設計・ビジョンを描くことを強みとするよう促されていると感じます。
「他人に影響を及ぼす」場面での人間力
後者の「他人に影響を及ぼす」は、生成AIに任すことは難しいと感じています。
売上拡大や生産性向上を目指す方法には、無数の選択肢があります。また売上拡大や生産性向上を他人に目指してもらうべく影響を与える方法も、目標を提示する、方法を教える、自分で考えさせるなど、様々な方法があります。表現方法として職場で公に発表する、個人的に話すの方法があり、その口調についても楽しげに話す、あるいは厳しめに話すなどがあるため、「他人に影響を及ぼす」選択肢は無数にあります。加えて、ある人に有効だった方法が、別の人には通用しない場合もあります。ある人に、ある時点では有効だった方法が、別の時点では通用しない場合さえあるのです。
「他人に影響を及ぼす」場面について生成AIは、求めれば無数の選択肢を挙げてくれるでしょう。しかし「有効な方法を選択する」ことについては、まだまだです。ある人、ある場面に最適な影響行使の方法を教えてくれるのは、もしかしたら永遠に来ないかもしれません。それが「人間」に絡むことだからです。
以上のように考えると、今後に人間と生成AIが共同・協働する姿が見えて来ます。人間は「人間力」の部分を担当し、強みを発揮することで、今までにない成果を実現できると考えられます。生成AIの使い方に精通すると共に人間力を磨いた人が、あるいは人間力を磨いた人が沢山いる組織が、今後に輝けるのだと考えられます。
本コラムの印刷版を用意しています
本コラムでは、印刷版を用意しています。印刷版はA4用紙一枚にまとまっているのでとても読みやすくなっています。印刷版を利用して、是非、未来を掴んでみてください。
【筆者へのご相談等はこちらから】
https://stratecutions.jp/index.php/contacts/
なお、冒頭の写真は ChatGPT により作成したものです。
プロフィール

落藤伸夫(おちふじ のぶお)
中小企業診断士事務所StrateCutions代表
合同会社StrateCutionsHRD代表
事業性評価支援士協会代表
中小企業診断士、MBA
日本政策金融公庫(中小企業金融公庫~中小企業信用保険公庫)に約30年勤務、金融機関として中小企業を支えた。総合研究所では先進的取組から地道な取組まで様ざまな中小企業を研究した。一方で日本経済を中小企業・大企業そして金融機関、行政などによる相互作用の産物であり、それが環境として中小企業・大企業、金融機関、行政などに影響を与えるエコシステムとして捉え、失われた10年・20年・30年の突破口とする研究を続けてきた。
独立後は中小企業を支える専門家としての一面の他、日本企業をモデルにアメリカで開発されたMCS(マネジメント・コントロール・システム論)をもとにしたマネジメント研修を、大企業も含めた企業向けに実施している。またイノベーションを量産する手法として「イノベーション創造式®」及び「イノベーション創造マップ®」をベースとした研修も実施中。
現在は、中小企業によるイノベーション創造と地域金融機関のコラボレーション形成について研究・支援態勢の形成を目指している。
【落藤伸夫 著書】
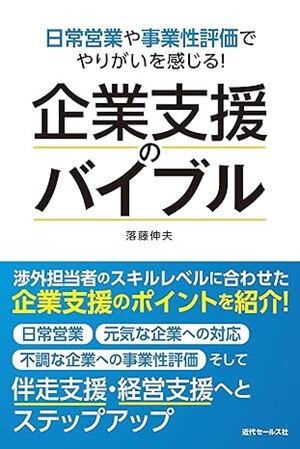
『日常営業や事業性評価でやりがいを感じる!企業支援のバイブル』
さまざまな融資制度や金融商品等や金融ルール、コンプライアンス、営業方法など多岐にわたって学びを続けながらノルマを達成するよう求められる地域金融機関渉外担当者が、仕事に意義を感じながら楽しく、自信とプライドを持って仕事ができることを目指した本。渉外担当者の成長を「日常営業」、「元気な企業への対応」、「不調な企業への対応(事業性評価)」、「伴走支援・経営支援」の5段階に分ける「渉外成熟度モデル」を縦軸に、各々の段階を前向きに捉え、成果を出せる考え方やノウハウを説明する。
Webサイト:StrateCutions
- 第83回 成長エンジンに乗る3要素を固める
- 第82回 成長エンジンに乗る決意を固める
- 第81回 価格理論破壊時代に油断する危険
- 第80回 通用しなくなりつつある経済原則:価格
- 第79回 未掴入口の捉え方
- 第78回 壁とするか、未掴への入り口とするか
- 第77回 生成AIを活用しながら人間力を発揮する
- 第76回 生成AIがもたらす革命的変化に対応する
- 第75回 100億宣言を実のあるものにする
- 第74回 100億宣言企業が募集されています
- 第73回 あいまいさを創造性に繋げる方法
- 第72回 あいまいさに耐えられない危険性
- 第71回 イノベーションの量産でジレンマ回避
- 第70回 イノベーションのジレンマは不可避か
- 第69回 激動の時代に「どのように」始めるか
- 第68回 激動時代に起業家の発想を取り入れる
- 第67回 トランプ関税を乗り越える産業・政策
- 第66回 トランプ関税を考えて今後を見通す
- 第65回 企業が描きたい大戦略
- 第64回 大戦略を描いていくことの大切さ
- 第63回 技術か経営かではなく、技術も経営も
- 第62回 ニッサン・ホンダの破談をどう捉えるか
- 第61回 社会システム変化の軸となる主体性
- 第60回 社会システム視座の必要性
- 第59回 再構築が望まれるエコシステムの姿
- 第58回 突きつけられる課題と、その対応方法
- 第57回 「好ましいインフレ」を目指す取組
- 第56回 「好ましいインフレ」を目指す
- 第55回 地域の未掴をエコシステムとして描く
- 第54回 地域の未掴はどのようにして探すのか
- 第53回 日本の未来を拓く構想と新しい機関
- 第52回 新政権に期待すること
- 第51回 日本ならではの外貨獲得力案
- 第50回 未掴を掴む原動力を歴史的に探る
- 第49回 明治時代の未掴、今の未掴
- 第48回 オリンピック会場から想起した日本の出発点
- 第47回 都知事選ポスターから考える日本の方向性
- 第46回 都知事選ポスター問題で見えたこと
- 第45回 閉塞感を打ち破る原動力となる「気概」
- 第44回 競争力低下を憂いて発展戦略を探る
- 第43回 中小企業の生産性を向上させる方法
- 第42回 中小企業の生産性問題を考える
- 第41回 資本主義が新しくなるのか別の主義が出現するのか
- 第40回 「新しい資本主義」をどのように捉えるか
- 第39回 日本GDPを改善する2つのアプローチ
- 第38回 イノベーションで何を目指すのか?
- 第37回 日本で「失われた〇年」が続く理由
- 第36回 イノベーションは思考法で実現する?!
- 第35回 高付加価値化へのイノベーション
- 第34回 2024年スタートに高付加価値化を誓う
- 第33回 生成AIで新価値を創造できる人になる
- 第32回 生成AIで価値を付け加える
- 第31回 価値を付け足していく方法
- 第30回 新しい資本主義の付加価値付けとは?
- 第29回 新しい資本主義でのマーケティング
- 第28回 新しい資本主義での付加価値生産
- 第27回 新しい資本主義で目指すべき方向性
- 第26回 新しい資本主義に乗じ、対処する
- 第25回 「新しい資本主義」を考える
- 第24回 ChatGPTから5.0社会の「肝」を探る
- 第23回 ChatGPTから垣間見る5.0社会
- 第22回 中小企業がイノベーションのタネを生める「時」
- 第21回 中小企業がイノベーションのタネを生む
- 第20回 イノベーションにおける中小企業の新たな役割
- 第19回 中小企業もイノベーションの主体になれる
- 第18回 横階層がイノベーションを実現する訳
- 第17回 イノベーションが実現する産業構造
- 第16回 ビジネスモデルを戦略的に発展させる
- 第15回 熟したイノベーションを高度利用する
- 第14回 イノベーションを総合力で実現する
- 第13回 日本のイノベーションが低調な一因
- 第12回 ミスコンから学んだ将来の掴み方(2)
- 第11回 ミスコンから学んだ将来の掴み方(1)
- 第10回 Futureを掴む人になる!
- 第9回 新しい世界を掴む年にしましょう
- 第8回 Society5.0・中小企業5.0実践企業
- 第7回 なぜ、中小企業も5.0なのか?
- 第6回 中小企業5.0
- 第5回 第5世代を担う「ティール組織」
- 第4回 「望めば叶う」の破壊力
- 第3回 5次元社会が未掴であること
- 第2回 目の前にある5次元社会
- 第1回 Future は来るものではない、掴むものだ。取り逃がすな!














