第74回
100億宣言企業が募集されています
StrateCutions (ストラテキューションズ)グループ 落藤 伸夫

政府がこの春から「100億宣言企業」を募集していることを、皆さんもご存じでしょう。この取組みは企業にとっても、そして地域ひいては日本にとっても「未掴を掴み取ろうとする」きっかけになると考えられます。今回はこのことについて考えてみます。
100億円企業を目指すということ
100億宣言とは何か?公式サイトには次のように説明されています。
<引用始まり>
「100億宣言」とは、中小企業の皆様が飛躍的成長を遂げるために、自ら、「売上高100億円」という経営者の皆様にとって野心的な目標を目指し、実現に向けた取組を行っていくことを、宣言するものです。
<引用終わり>
ここでのポイントは「売上100億円を目標とすること」、「実現に向けた具体的な取組みを行っていくこと」そして「それを宣言すること」です。このような宣言を行った企業を後押しするために政府は補助金や特別な税制を準備すると共に、100億宣言企業のネットワークを準備しました。
https://growth-100-oku.smrj.go.jp/
少なからぬ企業は成長を目指しており「(自ら定めた時期に)売上〇〇円企業になる」と目標を設定する場合もあります。中でも100億円は切れの良い数字なので魅力的ですが、さりとてどんな企業でも目指せる数字ではありません。
売上が100億円を超える企業は日本に2023年度現在15,159社しかなく、企業全体の1%に過ぎないからです。その範疇の企業になることを目指すとは、すなわち「野心的な目標」と言えるでしょう。
https://www.tdb.co.jp/report/economic/20250418-100okukigyo/(*)
「野心的な目標というより、今では非現実的な目標と言うべきだろう。失われた10年、20年、30年が進行中で逆風が吹いているのだから。」仰りたい趣旨、分かりますが、その逆風の中で100億円企業が増加していることに注目できます。上の調査(*)では、2023年度決算で初めて100億円の大台に乗ったのは609社、2022年度決算では641社でした。
「では新しい、成長中の企業なのだな。」これも、そうは言えないようです。同調査によると到達に要した平均年数(2023年度までの業歴)は42.2年でした。歴史ある企業でも成長を積み重ねて、あるいは成長のきっかけを掴んで100億円企業になったのです。
100億円企業になると宣言する意義
「逆風、あるいは『順風とは言えない』事業環境にあっても成長できる企業があるのは分かった。しかし成長には戦略が必要で、上手く策定する必要がある。当初は的確な戦略でも、事業環境の変化によっては調整が必要となるだろう。このような事情を踏まえると、100億円企業への成長は偶然の産物と言うべきだろう。」
確かに100億円企業の成長パターンには様々あり、ある報告書では自社開発、製品開発力(新製品企画)、自社ブランド、OEM供給、海外生産拠点、垂直M&A、水平M&A、販売方法の工夫、営業力強化、海外展開、多角化、付帯サービス強化という実に様々な(細かく見るとお互いに矛盾する策もある)などが挙げられていました。
https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/kenkyukai/seichoken/240628_report.pdf(※)
一方で上報告書(※)では成長パターンの選択よりも重要な要素として「経営者のモチベーション・成長志向」を挙げています。筆者としても、この指摘には納得ができます。
事業活動がコロナ禍により大きく阻まれ、その後に回復基調にあるがコロナ禍中に背負ってしまった財務問題が大きくのしかかっているので、コロナ禍以前なら「大した問題ではないね。しばらく耐えれば光明も差し込むだろう」と笑い飛ばせるような赤字が原因で存続の危機にある企業が、今後も持ち堪え、更なる回復を遂げて窮地を脱することができるようになるには、経営者の自覚(危機感)と「会社を立て直す、発展させるとの意思(覚悟)」がポイントになるからです。
この点で政府が「100億円企業になる」宣言を行うよう促したことは、とても意義のあることだと考えられます。調査(*)は2023年度以前3期の年商伸び率(平均)をもとに、現時点では100億企業ではない企業のうち2,398社が、2024年度以降3期以内に100億企業となる可能性が高い「ネクスト100億企業」に該当すると試算しました。
可能性があっても必ず成長できる訳ではありませんが、成長を宣言すると実現の可能性を高めることができます(加えて「中小企業成長加速化補助金」を活用できる可能性もあります)。宣言を事務局が確認済の企業数は1,419社(2025/7/7時点)で、8/25には追加確認企業が公表されました。
「次世代の輝かしい我が社」を積極的に掴み取ろうとする企業がこれほど存在することは、心強い限りです。
本コラムの印刷版を用意しています
本コラムでは、印刷版を用意しています。印刷版はA4用紙一枚にまとまっているのでとても読みやすくなっています。印刷版を利用して、是非、未来を掴んでみてください。
【筆者へのご相談等はこちらから】
https://stratecutions.jp/index.php/contacts/
なお、冒頭の写真は ChatGPT により作成したものです。
プロフィール

落藤伸夫(おちふじ のぶお)
中小企業診断士事務所StrateCutions代表
合同会社StrateCutionsHRD代表
事業性評価支援士協会代表
中小企業診断士、MBA
日本政策金融公庫(中小企業金融公庫~中小企業信用保険公庫)に約30年勤務、金融機関として中小企業を支えた。総合研究所では先進的取組から地道な取組まで様ざまな中小企業を研究した。一方で日本経済を中小企業・大企業そして金融機関、行政などによる相互作用の産物であり、それが環境として中小企業・大企業、金融機関、行政などに影響を与えるエコシステムとして捉え、失われた10年・20年・30年の突破口とする研究を続けてきた。
独立後は中小企業を支える専門家としての一面の他、日本企業をモデルにアメリカで開発されたMCS(マネジメント・コントロール・システム論)をもとにしたマネジメント研修を、大企業も含めた企業向けに実施している。またイノベーションを量産する手法として「イノベーション創造式®」及び「イノベーション創造マップ®」をベースとした研修も実施中。
現在は、中小企業によるイノベーション創造と地域金融機関のコラボレーション形成について研究・支援態勢の形成を目指している。
【落藤伸夫 著書】
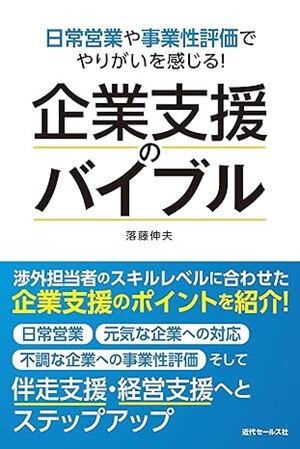
『日常営業や事業性評価でやりがいを感じる!企業支援のバイブル』
さまざまな融資制度や金融商品等や金融ルール、コンプライアンス、営業方法など多岐にわたって学びを続けながらノルマを達成するよう求められる地域金融機関渉外担当者が、仕事に意義を感じながら楽しく、自信とプライドを持って仕事ができることを目指した本。渉外担当者の成長を「日常営業」、「元気な企業への対応」、「不調な企業への対応(事業性評価)」、「伴走支援・経営支援」の5段階に分ける「渉外成熟度モデル」を縦軸に、各々の段階を前向きに捉え、成果を出せる考え方やノウハウを説明する。
Webサイト:StrateCutions
- 第83回 成長エンジンに乗る3要素を固める
- 第82回 成長エンジンに乗る決意を固める
- 第81回 価格理論破壊時代に油断する危険
- 第80回 通用しなくなりつつある経済原則:価格
- 第79回 未掴入口の捉え方
- 第78回 壁とするか、未掴への入り口とするか
- 第77回 生成AIを活用しながら人間力を発揮する
- 第76回 生成AIがもたらす革命的変化に対応する
- 第75回 100億宣言を実のあるものにする
- 第74回 100億宣言企業が募集されています
- 第73回 あいまいさを創造性に繋げる方法
- 第72回 あいまいさに耐えられない危険性
- 第71回 イノベーションの量産でジレンマ回避
- 第70回 イノベーションのジレンマは不可避か
- 第69回 激動の時代に「どのように」始めるか
- 第68回 激動時代に起業家の発想を取り入れる
- 第67回 トランプ関税を乗り越える産業・政策
- 第66回 トランプ関税を考えて今後を見通す
- 第65回 企業が描きたい大戦略
- 第64回 大戦略を描いていくことの大切さ
- 第63回 技術か経営かではなく、技術も経営も
- 第62回 ニッサン・ホンダの破談をどう捉えるか
- 第61回 社会システム変化の軸となる主体性
- 第60回 社会システム視座の必要性
- 第59回 再構築が望まれるエコシステムの姿
- 第58回 突きつけられる課題と、その対応方法
- 第57回 「好ましいインフレ」を目指す取組
- 第56回 「好ましいインフレ」を目指す
- 第55回 地域の未掴をエコシステムとして描く
- 第54回 地域の未掴はどのようにして探すのか
- 第53回 日本の未来を拓く構想と新しい機関
- 第52回 新政権に期待すること
- 第51回 日本ならではの外貨獲得力案
- 第50回 未掴を掴む原動力を歴史的に探る
- 第49回 明治時代の未掴、今の未掴
- 第48回 オリンピック会場から想起した日本の出発点
- 第47回 都知事選ポスターから考える日本の方向性
- 第46回 都知事選ポスター問題で見えたこと
- 第45回 閉塞感を打ち破る原動力となる「気概」
- 第44回 競争力低下を憂いて発展戦略を探る
- 第43回 中小企業の生産性を向上させる方法
- 第42回 中小企業の生産性問題を考える
- 第41回 資本主義が新しくなるのか別の主義が出現するのか
- 第40回 「新しい資本主義」をどのように捉えるか
- 第39回 日本GDPを改善する2つのアプローチ
- 第38回 イノベーションで何を目指すのか?
- 第37回 日本で「失われた〇年」が続く理由
- 第36回 イノベーションは思考法で実現する?!
- 第35回 高付加価値化へのイノベーション
- 第34回 2024年スタートに高付加価値化を誓う
- 第33回 生成AIで新価値を創造できる人になる
- 第32回 生成AIで価値を付け加える
- 第31回 価値を付け足していく方法
- 第30回 新しい資本主義の付加価値付けとは?
- 第29回 新しい資本主義でのマーケティング
- 第28回 新しい資本主義での付加価値生産
- 第27回 新しい資本主義で目指すべき方向性
- 第26回 新しい資本主義に乗じ、対処する
- 第25回 「新しい資本主義」を考える
- 第24回 ChatGPTから5.0社会の「肝」を探る
- 第23回 ChatGPTから垣間見る5.0社会
- 第22回 中小企業がイノベーションのタネを生める「時」
- 第21回 中小企業がイノベーションのタネを生む
- 第20回 イノベーションにおける中小企業の新たな役割
- 第19回 中小企業もイノベーションの主体になれる
- 第18回 横階層がイノベーションを実現する訳
- 第17回 イノベーションが実現する産業構造
- 第16回 ビジネスモデルを戦略的に発展させる
- 第15回 熟したイノベーションを高度利用する
- 第14回 イノベーションを総合力で実現する
- 第13回 日本のイノベーションが低調な一因
- 第12回 ミスコンから学んだ将来の掴み方(2)
- 第11回 ミスコンから学んだ将来の掴み方(1)
- 第10回 Futureを掴む人になる!
- 第9回 新しい世界を掴む年にしましょう
- 第8回 Society5.0・中小企業5.0実践企業
- 第7回 なぜ、中小企業も5.0なのか?
- 第6回 中小企業5.0
- 第5回 第5世代を担う「ティール組織」
- 第4回 「望めば叶う」の破壊力
- 第3回 5次元社会が未掴であること
- 第2回 目の前にある5次元社会
- 第1回 Future は来るものではない、掴むものだ。取り逃がすな!














