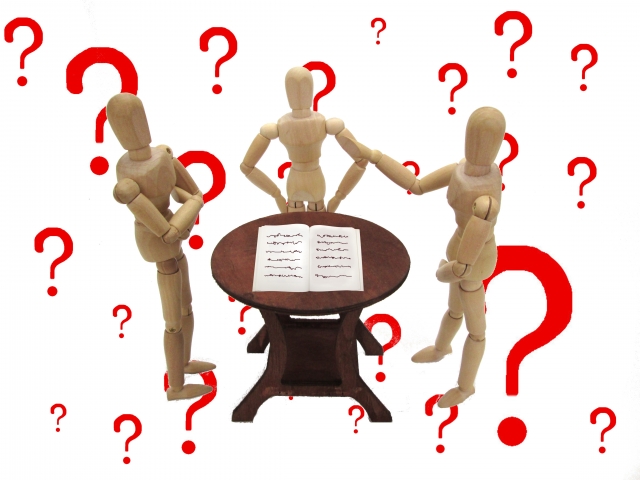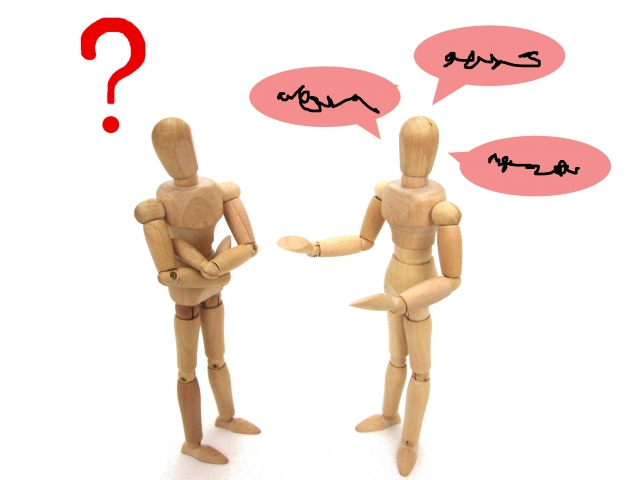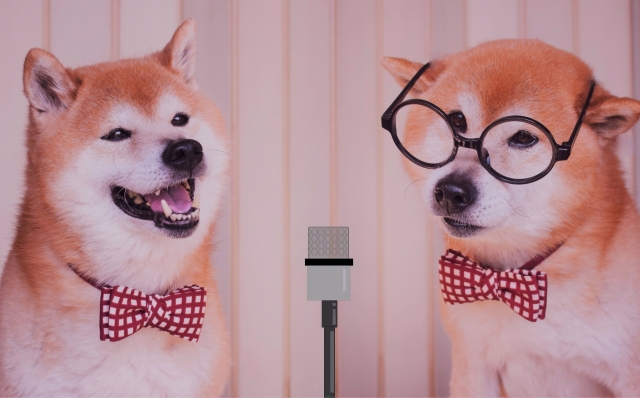会社千夜一夜
筆者:StrateCutions (ストラテキューションズ)グループ 落藤 伸夫

「日本中の会社に元気になってもらいたい。」StrateCutions代表落藤伸夫の強い想いから、連続コラム「倒産企業から事業改善を学ぶ!」はタイトルを変更して「会社千夜一夜(副題「あなたの代わりに貪欲に学ぶコンサルタントからの特別レポート)」としてお送りいたします。「会社を活性化したい」、「地域にもっと貢献できる企業になりたい」、「従業員も一緒に繁栄できる会社にしたい」と願う、中小企業のみならず大・中堅企業にも向けたメッセージです。なお「倒産企業から事業改善を学ぶ!」もサブリシーズとして継続してお送りします。
-
この師走は、モチベート策について考えてみました。今まで一般的に「恐怖によるモチベート策」が用いられてきましたが、逆効果やゲームズマンシップによる弊害などが指摘されています。これを避けるために勧められるのが「期待によるモチベート策」です。今日はこれについて深掘りして考えてみましょう。
.jpg)
-
そろそろクリスマスのカウントダウンが始まりました。会社によっては「誰でも5時から男・女(少し古いですかね)」になっている状況ではないでしょうか?いつもだったら「気を引き締めよう!」と言えば通じていたのに、今は「何それ?!」という反応を引き出しかねません。「こういう時は従業員を刺激しないよう、褒めた方が良いのだろうか?期待によるモチベートに似ているし。」管理職の皆さんから、そのような意見を聞くことがありますが、筆者としては「止めた方が良いでしょう」と答えています。今日は、褒めることと期待によるモチベートの違いについて、考えてみます。

-
12月に入って本格的に年末モードに入りました。先回、会社としてはスパート時期なのに働き手が乗ってこないこの時期のモチベーション維持・アップ策について考えたところです。恐怖によるモチベートと期待によるモチベートです。語られることは少ないようですが、非常に重要なポイントなので、今回はもう一歩、掘り下げて考えてみましょう。

-
最近は街頭の季節の変わり目が早く、ハロウィーンが終われば街はクリスマスに向かって染まっていきます。筆者が住む街でも11月半ばにはショッピングビルの玄関前に大きなクリスマスツリーが飾られました。この時期は実は、現場では年に何回かある「危ない季節」ではないかと思います。遊びの予定が重なったり、管理職が挨拶回りなどで外出しがちなどの事情で、現場の雰囲気が緩んでしまい、仕事に手に入らなくなってしまうのです。一方で会社としては、また契約先との関係でも、年末は締め切りになっていることが多い正念場です。ここで働き手のモチベーションをキープできるかどうかが、組織としての評価に大きく影響するといっても過言ではありません。今日は落ち着きを失いがちな時期にどうやってモチベーションをキープさせられるか、考えてみましょう。
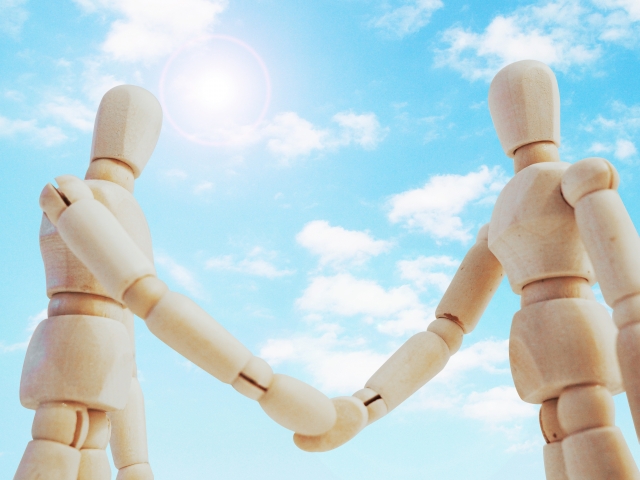
-
9月から10月にわたり日本に上陸・接近した台風を原因として関東を中心にした日本の広い地域で大規模かつ深刻な災害が発生しました。被害を受けられた皆様に心よりお見舞い申し上げます。一日も早い復旧を心よりお祈り申し上げます。復興に向けて店舗や工場の整備等は非常に大切なことですが、是非、資金繰りにも気を配って下さい。今回は、台風第19号で被災した中小企業等の皆さんへの支援として政府が発表した策(「災害救助法」による支援)についてお知らせします。

-
子どもにとっても大人にとっても啓発的な本、「Ai vs.教科書を読めないこどもたち(新井紀子)」をもとに、職場で起きている理解力のなさについて考えてきました。この記事をもとにいろいろな方と会話が弾み、Aiの専門家とは「Aiの理解力を向上させるために、何ができるか?」で盛り上がりました。そこで導き出された結果とは?

-
「最近、コミュニケーションが取れなくなってきたなあ」という声を多く聞きます。以前なら野球や歌謡曲など共通の話題をきっかけに話が弾み、そのまま仕事の話に繋げられることが多かったと記憶しています。今は情報が氾濫して共通の話題が少なくなりましたが、コミュニケーション不全の理由はそれだけではないようです。理解力の低下が原因かもしれません。今回は、ある会社の会議をもとに、この状況の理由と理解力低下の影響について、考えてみます。
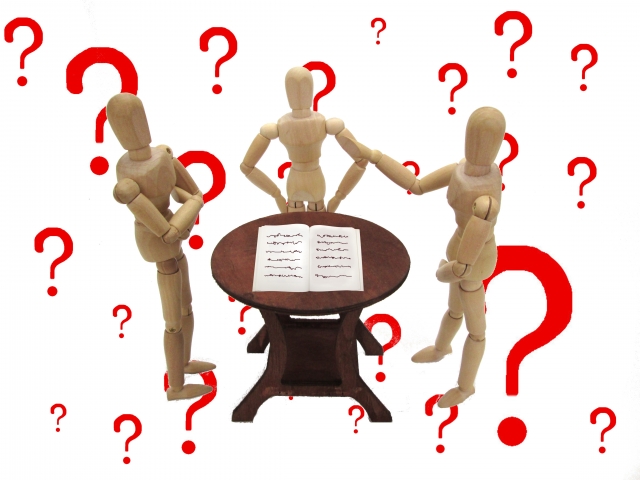
-
「AI vs. 教科書が読めない子どもたち (著者:新井紀子さん)」は、「コンピューターの理解力からすると、人間を追い越してしまう事態は当分、起きない」と結論づける一方で、逆に人間が理解力を落としてしまっていると警告しています。今回ももう一つ、日本の職場で多く発生していると考えられる現象について検討してみます。

-
しばらく前に、「AIによって人間の仕事がなくなる」という研究成果が発表され、波紋を起こしました。「コンピューターが人間を駆逐してしまう」という懸念もある中、最近、興味深い本を読みました。「AI vs. 教科書が読めない子どもたち (著者:新井紀子さん)」です。この本では「理解力」というキーワードから、AIだけでなく子どもたちに起きている問題に切り込んでいます。そして理解力の問題は、子どもたちばかりでなく会社でも起きていると考えられます。今回は、その一例を考えてみます。
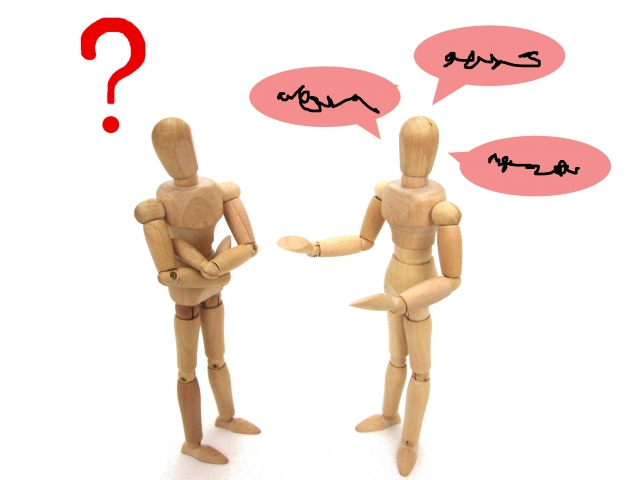
-
ここまで2回にわたり、吉本興業の「闇営業事件」から見えてきた、同社の上級マネジメントに内在する問題について考えてきました。今回は、皆さんの会社でも活用できる簡易チェックリストをご説明します。

-
先回記事で、所属芸人が反社会勢力のパーティー等に参加する「闇営業」をきっかけにバトル化してしまった吉本興業について、その真の原因が「上級マネジメントの不在にある」と指摘したところです。今回は、では吉本興業はどのような上級マネジメントを行うべきかを考えてみたいと思います。

-
関西のお笑いを発祥とする吉本興業に所属する何人かの芸人が反社会勢力のパーティー等に参加する、いわゆる「闇営業」を行なっていたことが社会の耳目を集めましたが、ここにきてある芸人が謝罪会見の席上で会社への不満をさらけ出したことで、吉本興業と芸人とのバトルの様相を呈しています。吉本興業が、闇営業を行わざるを得ないような低い給料しか払っていない場合があり、これが芸人たちを追い込んだというのです。今日は、なぜこんな事件が起きたのかについて考えてみます。
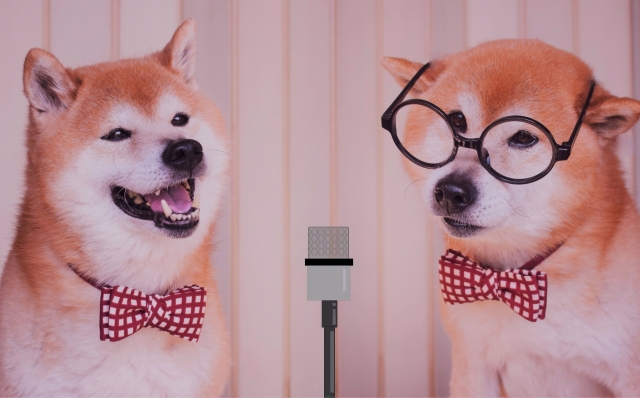
-
受講生への深い関心なくしてより良い人材開発、特に研修を考えることはできません。では、どんな関係を結べば良いのでしょうか?「受講生とは間接的な繋がりだから、良い関係も何もない。」そんなことはないと思います。今回は、人材開発担当が受講生と結ぶことのできる二つの関係について、考えてみます。
-
研修を改善していくには人事担当者と受講生との意識合わせが大切で、このため筆者は研修後に受講生と交流して意見を聞き出していました。事前に研修の目的や目標を伝えることができると、研修効果を更に向上させられると期待できます。一方で「事前のすり合わせは面倒なことが多い」と感じている人事担当者も多いようです。今回は、どのようにしたら効果的に事前のすり合わせができるかを考えていきます。
-
組織の側からと講師の側、人材育成のフィールドに両側から関わる立場に身を置いて痛感するのは「人材育成は、何のために行なっているのか」ということです。「社員に成長してもらうためだ。当たり前ではないか。」おっしゃる通りだと思いますが、毎年の振返り評価から次年度研修計画の際、そのジレンマに悩まされてきました。それはどんなことかというと・・・。
-
筆者はInnovationS-iコラムとして「未掴!」を発行しています。政府は、日本社会が質的に変化することを“Society5.0”を表現して提唱していますが、これは活躍する人材像も変わってくることを意味しています。では、どんな人材が必要とされるのか、考えてみましょう。
-
計画シーズンが終わって平時に戻ったら「どんな人材を育成したいか」を検討する時間を取りたいというのが、筆者の持論です。前回は「できること」アプローチではなく「あり方」アプローチで考えるようご提案しました。今回は角度を変えて「今、存在しない人材を育成していく必要性」という観点から考えてみたいと思います。人材を知らぬ間に「ゆでがえる」にしてしまった犯人が人材担当者だったということのないよう、「思考停止」から逃れるために是非ご検討ください。
-
史上最長10連休のGWが終わって一週間、だんだんと「平時」に戻ってきたのではないかと思います。「やっと今年のプランが動き始めた。しばらく進捗管理しておけば良い。腰を落ち着かせられる」とお考えの人材開発担当者も少なくないと思います。こんな時こそ考えてもらいたいことがあります。それは「我が社は、どんな人材を育てようとしているのか」という命題です。なかなか答えの出ない命題ではありますが、それを考えることで罠を避けることができます。それは何かというと・・・。
-
4月は「新体制がスタートした。頑張っていこう!」という意識が高まりますが、一方で、意外と見落とされがちなのが「新人研修」です。毎年、実施している内容が変わらないのです。研修担当者としては「社内向けで手一杯なのに、新人研修までゆっくりと考えていられない」という思いなのかもしれませんが、実はそこで大きな「遺失利益」が発生している可能性があります。今日は、カルサバ計画の実態とその脱却方法を、新人研修を題材に考えてみましょう。
-
先号で、人材開発計画を立てるにあたり陥りがちな罠として「カルサバ」をご説明しました。本連載コラムの読者は意図的に手を抜くことはない思いますが、いくつかのパターンを見る中で「近いことをしていたかも」と思った方もいるかもしれません。今回は、カルサバ計画がもしかしたら大変な結果に繋がる、すなわち担当者は楽ができるが会社が大きなツケを払わなければならない事態に陥る可能性があることについて、今回のコラムから読み取って頂ければと思っています。
-
2019年も3月の下旬となり、来年度に向けた人材開発計画が終盤を迎えている頃だと思います。年度内にトップの決裁を得るには、今がまさに努力のしがいがある時だと思いますが、「いやいや、毎年やっている仕事に、そんなに気合を入れて取組む必要はない。カルサバで良いんだよ。」そういうお話を耳にすることがあります。しかし、このような姿勢では決して会社にとってベストな人材開発はできません。今週は、カルサバの意味とどんな現象があるかを検討してみます。
-
「事業承継における2代目社長の人材開発」は、「広範性」、「現場体験の必要性」、「特殊性」、「組織依存性」などから「最も困難な人材育成」と言えそうです。企業の人材開発担当者も、この最も困難な人材開発から学ぶことができるでしょう。先週の検討を受けて、今週は、成果につながる取組みについて考えてみます。
-
「最も困難な人材開発は、誰を対象としたものだろう?」経営者や士業仲間の議論では「後継者の人材開発」となりました(「二代目社長の育成は、しばらく会社のナンバー2をやらせておけば良い」とはいかないようです)。最も困難な人材開発を観察すると、人材開発の本質についても見えてくるところがあります。それは何かと言うと・・・。
-
新年あけましておめでとうございます。本年も元気ある企業を目指して学びを続けてまいりましょう。新年1月1日の日本経済新聞第1面は「つながる100億の脳」、Fuji Sankei BUSINESS-iは「アジアとつながり飛躍目指せ」というタイトルでした。これらの記事は、ビジネス・パーソンにとってこれまで以上に学びが大切になることを示唆していると思われます。では、誰が、どんな学びを必要としているかというと・・・。
-
今月19日「平成最後の大型上場」との呼び声も高くSoftbankが東証1部に上場しました。孫社長は、どんな「魔法」を使って一代でSoftbankをここまで発展させることができたのでしょうか?今日は、その秘密について考えたいと思います(この記事はSoftbank株を買うようお勧めするものではありませんのでご注意ください)。
-
有価証券取引法違反などの疑いで逮捕されたカルロス・ゴーンから陰陽両面の教訓が得られると思います。先回は陽の教訓を考えてみました。彼の成功要因は「合理的なマネジメント」と「人を巻き込むリーダーシップ」だったのです。今回は陰の側面を考えてみます。但しそれはよく言われているような「高額な報酬」や「唯我独尊」ではなさそうです。では彼から何を学べば良いかというと・・・。
-
カルロス・ゴーンが有価証券取引法違反などの疑いで逮捕された事件は日本中を震撼させました。ゴーンが受け取ったとされる報酬や、そのうち有価証券報告書に記載されなかった金額の大きさに驚く人も多くいました。倒産寸前ニッサンの救世主とまで言われたゴーンと、今、このような嫌疑を受けて逮捕され、せっかく回復させたニッサンに大きな打撃を与えてしまったゴーンの両側面から、学ぶことは多いと思われます。ゴーン逮捕のショックが冷めやらぬ今、2週連続で考えてみましょう。
-
「穴を埋める人材育成」と「改善を目指す人材育成」という方法で人材難を乗り越えようとする時、教育から始めようとすると効果が出ない、もしくは逆効果になる可能性があります。環境整備が必要なのです。前回にご説明した環境整備に着手できたら教育を考えることができますが、どんな研修でも良い訳ではありません。「穴を埋める人材育成」と「改善を目指す人材育成」とマッチした人材教育とはどんなものかというと・・・。
-
人材難を乗り越えるには「穴を埋める人材育成」と「改善を目指す人材育成」という方法でアプローチできるかもしれません。この方法を活用することで「いつ、誰が会社を辞めてしまうのだろう。そうしたら業務はどうなってしまうのだろう」という不安を解消してくれる拠り所が得られる可能性があります。では「穴を埋める人材育成」と「改善を目指す人材育成」はどのようにして実現できるかというと・・・。
-
最近、人材難が強く叫ばれています。中小企業の倒産は、これまで数年間減少傾向でしたが今年は増加に転じる可能性が高く、その原因は人材難と言われています。確かに、筆者がご支援している企業も欠員の補充ができなくて困っています。今回は、人材難について人材育成の観点から考えてみましょう。
-
最近、注目した記事があります。10月1日のFuji Sankei Business i トップ記事は「ドローン物流 ANAのやる気」でした。国土交通省と環境省が連携募集した「ドローン(小型無人機)物流」実証実験の事業者にANAホールディングスが選ばれ、2020年代の実用化を目指した実証実験を年内にも始めるそうです。なぜANAはチャレンジしたのでしょうか?これが一つのイノベーションとなると考えたからでしょう。それはどういうことかというと。
-
現在、人手不足が非常に問題になっています。もともと人材の確保が難しい中小企業では、この問題は非常に深刻で、筆者の周囲にも困っている企業がたくさんあります。今回は、人手不足にどう対応するかについて考えたいと思います。
-
中小企業支援の仕事に関わっていると、今や、起業者への支援を欠かすことはできません。国も力を入れて起業者を応援しています。一方で、起業者の状況は決して順調とは言えません。統計を見ると多くの企業が起業後数年で廃業に追いやられています。どうすればこれを改善できるか、考えてみると、起業家には犯しやすい間違いがあるように感じられます。それは何かというと・・・。
-
元気な中小企業、いや大企業も含めて、そういう企業に働く人々の表情は明るく、大きな声で挨拶していると感じられます。実際、大きな声での挨拶が大流行で、取り組んでいない会社・店舗の方が少ない感じです。しかし、大きな声での挨拶ができれば必ずお店・会社が元気になるかというと、そうでもなさそうです。もっと大切なポイントがあります。それが何かというと・・・。
-
本コラムはこれまで「倒産企業から事業改善を学ぶ ~元倒産審査マンが教える繁栄企業へのメソッド~」としてお送りしてきましたが、今回から名称を改めて「会社千夜一夜 ~あなたの代わりに貪欲に学ぶコンサルタントのレポート~」としてお送りいたします。このような変更を考えたのは、コンサルタント及び研修講師としての私の知識・ノウハウを、もっと活用してもらいたいと考えたからです。そういう想いを、今回はお伝えします。
-
事業は「労働集約型」と「資本集約型」の2種類に分類され、「労働集約型ビジネスの場合には従業員満足が大切だが、資本集約型の場合には最新の機械・設備の充実がポイントである」と言われたりします。決して間違いとは思いませんが、だからといって資本集約型ビジネスで従業員を軽視して良いとは限りません。逆に、従業員軽視が会社に致命的なダメージを与える場合もあります。どういうことかというと・・・。
-
起業支援する多くの方々が「多くの士業・先生業が創業するが、その多くがかなり短い期間で廃業に追い込まれている」と指摘しています。「知識もあり、判断力もある人たちなのに、なぜ、そんなに廃業に追い込まれるのだろうか?」その質問の答えに心当たりがあります。先生業を目指す方は「準備に忙しい」ケースがあるからです。事業を成功させるためには準備は必要ですが、その「やりすぎ」は落とし穴になる可能性があります。どういうことかというと・・・。
-
「企業経営には経理が不可欠」という言葉を耳にする時があります。簿記の知識が必要だという意味ではありません。でも、儲かっている企業の社長さんはほとんど例外なく「経理」について鋭敏な感覚をお持ちです。経理感覚がないとどんなことが起きてしまう可能性があるのでしょうか?ある雑貨店のケースから考えてみます。
-
第11回 周囲を蹴落としたら自分の所在もなくなってしまったケース
地方のみならず大都市圏でも「シャッター街」問題は深刻です。減りゆくお客様を「自分だけは確保したい」と考える気持ちも理解できますが、多くの場合、それは回り回って自分の首を絞めることになります。「自分だけ」の発想が時には大きなツケとして巡ってくる可能性があることや、それを防ぐ発想法について検討してみます。
-
第10回 お金の使い方でサラリーマンから卒業できなかったケース
サラリーマンを「卒業」して独立起業する方が増えている動きには、中小企業数が激減している中、日本経済を支え、子供達の世代に元気な社会を引き継いでいく原動力として、とても期待しています。壮年サラリーマンが身に付けた技能・ノウハウを、会社を辞めて起業することで自ら創造することは、とても素晴らしいことだと思いいます。一方で、そういうサラリーマンから起業した方々を拝見していると「お金の使い方でサラリーマンを卒業できなかったケース」を散見します。それは、時には独立起業の夢を打ち砕く可能性さえあります。今回は、こういうケースを検討します。
-
第9回 事業承継への消極性が企業の持続力を奪ってしまったケース
事業承継を考えてもおかしくないお年頃の社長さんとお話をすると「事業承継するかどうかは自分では決められない。後継者候補が『会社を継ぎたい』と言ってくれるまで頑張るしかない。彼が会社に失望しないよう、リスクは取れない」というお話をお聞きすることがあります。もっともなお話ですが、その方針が会社を倒産に至らせる場合もあります。今回は、そんなケースを検討します。
-
現在、政府が事業承継を強力に後押ししています。二代目候補が「これならいける」と考えるビジネスモデルを描き、それを前提に事業承継するのは、とても望ましい姿です。しかし、それにも落とし穴がない訳ではありません。今回は多店舗戦略を例に、ありがちな落とし穴と回避方法を考えていきます。
-
倒産審査マンとして多くみかける倒産パターンの一つに「リスケ後、返済を再開せざるを得なくなった時に資金ショートしてしまう」があります。「もともと返済できなかったからリスケしたんだ。1年経っても状況は変わらなかったのだろう。そこで返済を強要するなんて、金融機関も冷酷だな。」そういう感想をお持ちの方もおられるでしょう。しかし、実際は、何が起きているのでしょうか?
-
「堅実経営」は尊敬すべき経営の姿ですが、最近はバランス感覚が必要なようです。顧客の求める製品・サービスの提供や業務の効率化などに必要不可欠な投資を怠ると、自らを窮地に追い込みかねません。どういうことかというと・・・。
-
今、日本の企業数が急激に減少しており、その原因の一つとして経営者の高齢化などによる廃業が挙げられています。事業承継には「後継者不足」「株式の承継」などの問題もありますが、もう一つ、「二代目社長の経営力」も問題になる場合もあります。有能な二代目が陥ってしまいがちな罠もあるのです。今回は、その罠と対策についてご説明します。
-
抜本的な経営改善に努めなければならない企業の最大の敵の一つに、「素人からの甘い助言」があるかもしれません。例えば、瀕死ともいえる企業でもインターネットのホームページを改善すれば、いとも簡単に復活できると言うのです。しかしそれは絵空事に過ぎません。では、どんな策が必要かと言うと・・・。
-
特定の金融機関からの借入が増えて「支店長決裁」限度を超えると「本部審査部決裁」となりますが、この場合は提出を求められる書類が増えたり、事業計画書を求められる場合があります。しかし「これを嫌って他の金融機関の門を叩く」ことを続けていると、致命的な結果に至る可能性があります。それはどういう意味かというと・・・。
-
第2回 仮説に固執して事業改善のタネを見付けきれなかったケース
倒産企業を多数、審査していると、「なぜ、手が付けられなくなる前に事業改善に取り組もうとしなかったのだろう?」と思う案件に遭遇することが少なくありません。仔細に調べていくと見えてくることがあります。「原因を見極められないため、対策が打てない」という事情です。対策を打つためには原因究明が大切ですが、原因が分からないからといって放置していると手遅れになる場合があります。では、どうすれば良いかというと・・・。
-
2018年を迎えるにあたってStrateCutionsでは、StrateCutionsらしい、しかし今まで行なっていなかった新しい取組みを行うことにしました。代表者である落藤が前職で「倒産審査マン」だった間に培った知識・ノウハウをみなさんにお伝えすることです。倒産企業から学ぶのです。倒産企業から学ぶことにより、企業には意外な落とし穴があることや、事業改善のタネがあることに気が付くことができます。これらを活かすことで、是非、繁盛企業を目指してまいりましょう!
プロフィール

StrateCutions
代表 落藤 伸夫
1985年中小企業信用保険公庫(日本政策金融公庫)入庫
約30年間の在職中、中小企業信用保険審査部門(倒産審査マン)、保険業務部門(信用保証・信用保険制度における事業再生支援スキーム策定、事業再生案件審査)、総合研究所(企業研究・経済調査)、システム部門(ホストコンピューター運用・活用企画)、事業企画部門(組織改革)等を歴任。その間、2つの信用保証協会に出向し、保証審査業務にも従事(保証審査マン)。
1999年 中小企業診断士登録。企業経営者としっかりと向き合うと共に、現場に入り込んで強みや弱みを見つける眼を養う。 2008年 Bond-BBT MBA-BBT MBA課程修了。企業経営者の経営方針や企業の事業状況について同業他社や事業環境・トレンドなどと対比して適切に評価すると共に、企業にマッチし力強く成果をあげていく経営戦略やマネジメント策を考案・実施するノウハウを会得する。 2014年 約30年勤めた日本政策金融公庫を退職、中小企業診断士として独立する。在職期間中に18,000を超える倒産案件を審査してきた経験から「もう倒産企業はいらない」という強い想いを持ち、 企業を強くする戦略策定の支援と実行段階におけるマネジメント支援を中心した企業顧問などの支援を行う。
2016年 資金調達支援事業を開始。当初は「安易な借入は企業倒産の近道」と考えて資金調達支援は敬遠していたが、資金調達する瞬間こそ事業改善へのエネルギーが最大になっていることに気付き、前向きに努力する中小企業の資金調達支援を開始する。日本政策金融公庫で政策研究・制度設計(信用保証・信用保険制度における事業再生支援スキーム策定)にも携わった経験から、政策をうまく活用した事業改善支援を得意とする。既に「事業性評価融資」を金融機関に提案する資金調達支援にも成功している。
Webサイト:StrateCutions

.jpg)