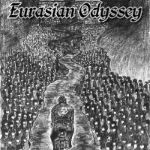第83回
「いろんな引き出しを持つ」宮嶋明香さん
ピーエムグローバル株式会社 木暮 知之
さまざまな分野で活躍する方にお話を伺うインタビュー「グローバル・コネクター®」。今回のゲストは、国内外で20年以上ソプラノ歌手として活躍する傍ら、日本に駐在する外国人ビジネスマンの日本語教師としても活動する声楽家の宮嶋明香さんです。
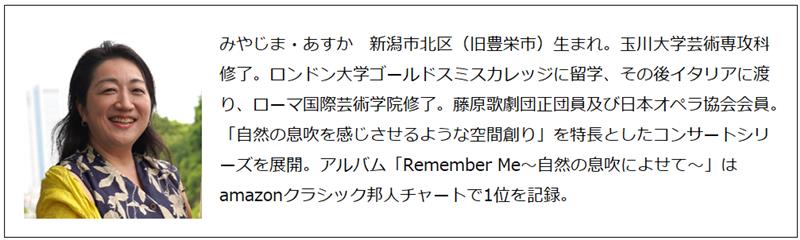
木暮 ご家庭は「音楽一家」ではなかったそうですね。
宮嶋 はい、新潟市にあります和食店「みやじま」の長女として生まれました。地元の人に来てもらうような店です。父は2年前に他界しましたが、今も母が従業員の人たちと店を切り盛りしています。たたき上げで商売をやってきた両親の背中を見て育ちました。ゆくゆくは跡取りにしたかったみたいですが、店を継がないなら地元で教師か看護師のような安定した職に就くことを望んでいたようです。
木暮 高校進学が転機になったと聞きました。
宮嶋 そうした親の期待とは裏腹に「外の世界を見たい」と思っていたので、海外ホームステイ体験をはじめ、自由なことが学べる機会がたくさんありそうな県内の敬和学園高校に進みました。自然豊かな環境で、学校には個性的な先生が多く、初日から「君たち、変な人になりなさい」と言われたり、生徒そっちのけで全編英語で授業を進められたりして刺激的でした。米国でのホームステイ合宿も経験できました。
木暮 僕も高校生の時に米国に留学して視野が広がりました。初の海外はどうでしたか。
宮嶋 到着早々にホストファミリーとサマーキャンプに行ったりして日々、米国文化を満喫しました。夕飯として食卓に出てきたのがソーセージとポテトチップスだけだったり、滞在先の7歳の娘さんからキスの嵐を受けて圧倒されたりしたのも良い思い出です。
木暮 音楽家を目指されたのも高校の部活動がきっかけ。
宮嶋 自分が打ち込めるような何かを見つけたいと思い、コーラスや合唱をする声楽部に入りました。そこで音楽や歌が大好きになって、ずっと歌っていたい、歌をもっとやっていきたいという気持ちが広がっていきました。歌うことや音楽が勉強できる大学に進もうと顧問の先生に「歌がやりたいです。音楽を続けたいです」と相談したら、先生はそのまま黙り込んでしまって。不穏な静寂が1分ぐらい続いたでしょうか、先生から出た言葉は「大丈夫、かもしれない」でした。
木暮 否定されなかった。先生なりに、すごく考えられたんですね。
宮嶋 外に雨音が響く中、黙って考えていらした様子は今でも思い出します。音楽の英才教育を受けてきたわけでもなく、高校から音楽を始めただけで、音楽的な礎(いしずえ)がないまま険しい道を選ぼうとしているから、苦労するのが目に見えていたんでしょうね。でも、声質や音楽家としての素養、可能性を見出してくれる人は当時、先生しかいませんでしたから、あの時「やめた方が良い」と言われていたら、勇気を出して音楽の道に挑戦していなかったと思います。両親からは現役合格を条件に受験を許され、それから猛勉強の日々でした。何人かの音楽専門の先生方や仲間たちにも助けられました。
木暮 努力の甲斐あってめでたく大学に合格。晴れて東京で音楽の勉強を。
宮嶋 玉川大学は、芸術分野の教育で定評のある英ロンドン大ゴールドスミス校と姉妹校提携をしており、卒業後はすぐ渡欧して、本場の音楽を学びたいと学生時代から思っていました。イタリアを拠点にプロの伴奏ピアニストとして活動していた大学の先輩に、自分の欧州留学志向を伝えると「行ってもコテンパンされるだけ。今は自分のレパートリーを固めた方が良い」と諭されました。その後、渡欧できることになり、ロンドンやローマに留学し、先輩にもお世話になりました。
木暮 レパートリーとはどんなものですか。
宮嶋 声質に合わせ、自分の得意な曲をまとめていくんです。例えばモーツァルトの声質だったら同時代のほかの作曲家の作品など、自分の特性に合ったものを見つけて、いいところをどんどん磨いていく。日本での学生時代に欧州へ短期留学したことがあったのですが、現地の先生からは「あなたのレパートリーは野菜かごみたい」と言われました。当時は自分でも何が得意なのか分かっていなかったんですね。
木暮 その後、本格的に留学。
宮嶋 声楽の場合、留学のタイミングは喉が育つまでは難しいんです。また説得力を持って歌詞を伝える人生経験や感情表現が求められます。渡欧して分かったのは、自分のレパートリーを確立しないと潰れてしまう人の方が多いということ。小さい頃から自分がどう思うか、を親から教えられて育ってきた欧米の人と違い、日本人の場合、先生の指示通りにできるのをよしとする傾向があります。自分の意見を伝える訓練を受けていないから留学してもうまくいかない。先輩の真意は、自分のアイデンティティがないと難しい、ということだったのだと後で分かりました。

木暮 何でも歌えるオールラウンダーはいないのですか。
宮嶋 歌に関して言えば、喉が壊れてしまいます。声楽を始めたばかりの人たちは、喉の動かし方も習っている段階。例えば、走り方とか運動の技術も学んでいないアスリートがいきなり試合に出ても、体が壊れてしまいますよね。欧米では先生が生徒の声質に合うレパートリーを作ってくれるんです。 自分の声に合うものを歌うと、ものすごく技術が伸びていくんです。モーツァルトやヘンデルなどが私は得意で、ソプラノの中でも柔らかく、抒情的な曲をレパートリーにしている「リリコソプラノ」です。
木暮 奥が深いですね。日本だと満遍なくできる「平均点の高い人」が評価されがちです。欧米では生徒の特性を見定めて、それを伸ばすように指導するし、本人たちもそれを武器に生きていく。その発想はすごくいいなと思います。
日本語でつながる
木暮 声楽家として欧州で研さんを積まれ、プロとして活躍されていらっしゃる一方、日本語教師としての顔もお持ちです。
宮嶋 ロンドン大学の社会人コースで学んでいた時に、日本語クラスのアシスタント募集があり、応募したのがきっかけです。日本語を学びに来る人は「それぞれの日本」に憧れていることを知ったのが新鮮な驚きでした。西洋音楽に憧れていた私と同じように、彼らはアニメや日本文化に興味を持っている。当時は一生懸命に西洋人になろうとしていた部分もあったのですが、「日本人としての自分も大事にしなきゃいけない」「自分を日本人と認識した上で表現できるものがある」と気付かされたんです。彼らとのコミュニケーションがすごく面白くて、日本語教師もやってみたいと思いました。滞在中は音楽の勉強が主なので、本格的に日本語教師を仕事として始めたのは帰国してからです。声楽家も日本語教師も人と人とのつながりがあるし、その後は仕事のジャンルもあまり考えないようになりました。
木暮 コミュニケーションが面白い、というのはいろんな考えや思いも寄らない発想に出合えるのが楽しいということでしょうか。一方でそれが苦手だったり、戸惑ったりする人もいます。最近ではインバウンド(訪日外国人)との関わり方も注目されるようになっています。多様な意見と持つ人たちと向き合う上で工夫されていることはありますか。
宮嶋 いろんな引き出しを持って「演技する」ことでしょうか。人によっては、自分が理解されないかな、という場合もあります。相手の状況を見極め、関係性を円滑にするために、どういう自分になればいいかを考えてその人に合わせる。日本語レッスンの場合は、依頼主がどんな人か分からない中で、相手が到達したいゴールに合わせたものを提供しなければいけません。ただ、音楽に関しては別です。ステージでは、妥協することなく表現したいものに向き合い、音楽を共に創ります。とはいえ、両者には共通点もあります。空間とハーモニーを創って感動を共有する、という意味で向き合い方は同じです。
木暮 その場で求められる役割を意識するという感覚は分かります。個人的にはユーモアをもって楽しくみんなで和気あいあいとやりましょう、というのが得意なんです。以前、欧州の大企業の経営陣が参加する会議で、普段通りのソフトな感じで発言したら、その場がものすごく「寒い」雰囲気になったことがありました。
宮嶋 色々な人がいるのは面白くもあります。今日はどの「チャンネル」でいけばいいんだろう、みたいに、さまざまな自分になれて楽しい。依頼主の中には、外国企業で重役を務める方もいるのですが、彼らも大変なようです。イエス・ノーをはっきり言う文化の国から日本にやってきてイエス・ノーを言わない人たちを動かさなくてはいけない。「意思をはっきり示さない社員たちのメンタリティが分からない」と、こぼす人もいます。例えば、日本人は「いいえ」という返事をあまり使いませんよね。提案を断ったり、意見を否定したりするときは「それはちょっと…」という言い方のほうが多い。日本人から「ちょっと…」と言われたら、意味としてはノー。だけど、実は何か他に言いたいことがあるんですよ、と伝えています。
木暮 まさしく。面白いですね。
宮嶋 音楽でコミュニケーションを取りたいし、人ともコミュニケーションを取りたい。声楽も言語も私にとっては、つながっているんです。
木暮 音楽も一方通行的な表現ではない、つながる楽しさがあるということですね。
宮嶋 そうなんです。ジャンルにとらわれない演奏家とのコラボレーションや音楽イベントが好きですし、ミュージシャンのいる舞台と空間と聴衆が一体になるコンサートの方がいいと思って活動しています。聴衆はすごくパワーをくれるんです。コンサートに行くのはリラックスしたかったり、感動したかったりと、誰もが何かを得たいからです。時間と場所を共有してくれるわけですから、その瞬間を共に創造したいという気持ちがありますね。それは「調和」なのかもしれないです。そうした空間を、ひとつひとつ今後も創っていきたいですね。(おわり)
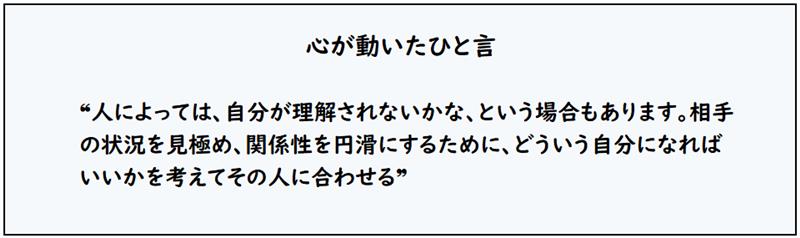
宮嶋明香さんについては当社のFacebookでもご紹介しております。ぜひご覧ください。
自由な芸術空間づくりを得意とする宮嶋明香さんが2021年から手掛ける「自然の息吹コンサート」が今年10月31日に東京・五反田文化センター音楽ホールで開催されます。「自然の息吹コンサートVol.5」の詳細はこちらをご覧ください。
プロフィール

グローバルなビジネス環境で今まで以上に高品質なプロジェクトマネジメントを必要とされる全てのお客様のために、プロジェクトを推進し成功させるための環境づくりを総合的にサポートします。また、マネジメントのパートナーとして現場の視点と経営の視点を併せ持った課題の発見、およびその対策としての戦略策定をご提案します。
【サービスメニュー】
プロジェクトのマネジメント支援(PMO)
プロジェクトマネージャーのトレーニング
セミナー「グローバル・コネクター」の開催・運営
グローバル人材の育成
海外拠点の現地社員育成
インドニュースの配信・出版
ニュース配信サイトの運営
海外進出コンサルティング
Webサイト:ピーエムグローバル株式会社

「外国の方とのビジネスやコミュニケーションに悩まれたことはありませんか?
ギクシャクしたり、思ったほど相手との距離が縮まらなかったり。英語だけの問題ではないのでは?
『ガイバナ』では、英会話自体にフォーカスするのではなく、英語が苦手な方でも、一歩踏み出してコミュニケーションの場を明るくする、キラリと光るエッセンスをお届けします。エピソード後半に、覚えてほしいキラリフレーズをご紹介しています。
「ガイバナ」ポッドキャストはこちらから
ガイバナ@Line: @315pjfpo」
- 第84回 「目の前の人を幸せに」鈴木亮子さん
- 第83回 「いろんな引き出しを持つ」宮嶋明香さん
- 第82回 「義理人情は世界共通」東福寺厚樹さん
- 第81回 「自分を信じる」志村真里亜さん
- 第80回 「素直に教えを乞う」尾﨑洋平さん
- 第79回 「苦楽を分かち合う」渡邉哲夫さん
- 第78回 「変えたいならチャレンジ」前田謙一郎さん
- 第77回 「みんなで決めたらやり遂げる」甲斐ラースさん
- 第76回 「ひとつずつクリアする」大渕愛子さん
- 第75回 「国内・海外の共通言語はコミュニケーション力」駒井愼二さん
- 第74回 「相手に合わせたロジックを」福田勝さん
- 第73回 「強みを生かす」亀井貴司さん
- 第72回 「現状に疑問を持つ」アミヤ・サディキさん
- 第71回 「任せたら自由にさせる」竹内新さん
- 第70回 「正しいあうんの呼吸を」村瀬俊朗さん
- 第69回 「ほかにない価値を」金城誠さん
- 第68回 「素早く対応する」柏田剛介さん
- 第67回 「ビジョンを伝える」中村勝裕さん
- 第66回 「歴史を学ぼう」磯部功治さん
- 第65回 「多少の自信と歯切れの良さと」島原智子さん
- 第64回 「情報を体系化する」鈴木隆太郎さん
- 第63回 「メッセージを明確に」岩本修さん
- 第62回 「上司もホウ・レン・ソウ」高橋裕幸さん
- 第61回 「自分を肯定する」前川裕奈さん
- 第60回 「状況を掘り下げて原因を探す」寺島周一さん
- 第59回 「信頼と共感の空気をつくる」蔭山幸司さん
- 第58回 「一緒に楽しむと続けられる」草木佳大さん
- 第57回 「7割の見込みを信じる」吉元大さん
- 第56回 「意見をありがたく聞く」室井麻希さん
- 第55回 「常に学び・成長できる環境に身を置く」門田進一郎さん
- 第54回 「目の前の人との関係を大事に」岡田昇さん
- 第53回 「意見を聞いてから主張を調整する」大橋譲さん
- 第52回 「頼れる存在に任せる」ケビン・クラフトさん
- 第51回 「要望の背景も話す」堀田卓哉さん
- 第50回 「素直に聞く度量を」山田剛さん
- 第49回 「奇妙な日本人を自覚する」村上淳也さん
- 第48回 「信頼にめりはりを」二階堂パサナさん
- 第47回 「俯瞰(ふかん)して眺める」エドワード・ヘイムスさん
- 第46回 「丁寧さが評価される」ブレケル・オスカルさん
- 第45回 「個と向き合う」吉野哲仁さん
- 第44回 「事実に焦点を当てる」中村敏也さん
- 第43回 「現場に顔を出す」深井芽里さん
- 第42回 「状況を楽しむ」飯沼ミチエさん
- 第41回 「人生を楽しむ“絶対的価値観”を」小川貴一郎さん
- 第40回 「少ない言葉でも伝わる」アレン・パーカーさん
- 第39回 「ポジティブは伝染する」川平慈英さん
- 第38回 「自分で考える人に」野田純さん
- 第37回 「常にフェアであれ」忍足謙朗さん
- 第36回 「相手の価値観を包み込む」神原咲子さん
- 第35回 「直接得る情報を大事に」ネルソン水嶋さん
- 第34回 「相手のルールを早く知る」杉窪章匡さん
- 第33回 「意見を受け入れて試してみる」鈴木皓矢さん /「ノーと言われてもあきらめない」林祥太郎さん
- 第32回 「技術を尖(とが)らせる」稲垣裕行さん
- 第31回 「自分でやってみる」佐々木英之さん/「やる気のエネルギーを信じる」白井良さん
- 第30回 「リフレッシュ方法を見つける」大野均さん
- 第29回 「英語はメールから始めよう」岡田陽二さん
- 第28回 「逃げずに向き合う」矢野浩一さん
- 第27回 「相手に合わせた伝え方を」松田励さん
- 第26回 「ゴールを共有する」多島洋如さん
- 第25回 「考え方は変えられる」小森谷朋子さん
- 第24回 「相手が話しやすいテーマで心をつかむ」増山健さん
- 第23回 「どうしたいかで生きればいい」佐藤みよ子さん
- 第22回 「伝わる話題を探す」石井陽介さん
- 第21回 「話をよく聞いて信頼してもらう」我謝京子さん
- 第20回 「ギブアンドテイクの視点で」北尾敬介さん
- 第19回 「組織はファミリー」中沢宏行さん
- 第18回 「1人のスーパーマンよりチームワーク」前澤正利さん
- 第17回 「多様なメンバーが強い組織を生む」竹田綾夏さん
- 第16回 「ビジョンを共有する」マックス市川さん
- 第15回 「同じ人間として対等に話す」浦川明典さん
- 第14回 「会話は敬語、メールは気配り」イムラン・スィディキさん
- 第13回 「思い込みを捨てる」羽田賀恵さん
- 第12回 「うじうじ考えてないでサッサやるだけよ」本多士郎さん
- 第11回 「批判だけでは前に進まない」チャンダー・メヘラさん
- 第10回 「実績を示せば耳を傾けてもらえる」朝野徹さん
- 第9回 「シナジーをいかに引き起こすか」髙谷晃さん
- 第8回 「交渉は役割分担と演出で」新谷誠さん
- 第7回 「相手のプライドを土足で汚さない」佐藤知一さん
- 第6回 「気持ちが入っていないと、いい仕事はできない」 森本容子さん
- 第5回 「知る、理解する、好きになる、の順で」原田幸之介さん
- 第4回 「人に会って信頼できるネットワークをつくる」齊藤整さん
- 第3回 「失敗はだれでもある、やり直せる」平野昌義さん
- 第2回 「『好き』が相手に伝われば何とかなる」林原誠さん
- 第1回 「アドレナリンが出ている時が大事」太田悠介さん