第2回
「共創型」を企業が必要とする理由
StrateCutions (ストラテキューションズ)グループ 落藤 伸夫

新コラム「共創型金融の時代!あなたはビジョンを描けますか?」をスタートした理由について、創刊号では中小企業を巡る状況、特に金融環境からご説明しました。本号では中小企業サイドでも事業性評価から共創型へのシフトが必要となる理由について、考えていきます。
事業性評価では対応してもらえない会社がある
「事業性評価とは何か?誰がするのか?」答えは「融資における審査手法であり、金融機関が行う」です。しかし、金融機関だけの意識や工夫のみで事業性評価が行える訳ではありません。スコアリングという客観的かつ過去実績を踏まえた審査手法により導き出された「この企業には融資は難しい」との結論を、手持ちの情報だけで覆すのは困難です。
より詳しい定量分析や定性分析が必要で、そのためには新たな情報が不可欠です。この意味で事業性評価では中小企業の積極的な関与が必要で、従前コラム「事業性評価が到来!あなたは資金調達できますかplus」では、そのことをお勧めしていました。
一方で今、事業性評価では資金調達できない企業が増えています。コロナ禍時代に今までにない資金支援を受けて倒産を回避できた企業の中には、今でも完全復調には至っていない企業があります。
これら企業が借りたお金の流出が原因で債務超過になっていると、金融機関としては事業性評価を行っても資金援助は難しいのです。
実現性のある事業計画が必要だが難しかった
では苦境にありながらも生き残りを模索、回復基調に乗りたいと考える企業は、どうすれば良いのでしょうか?
「万策尽きた。事業性評価に対応してもらおうと事業計画も立てたが『この数字が実現できる理由を教えて欲しい』との質問に答えに窮していると『それでは融資は難しい』と言われてしまったからだ。」このような場面に直面した企業は多いでしょう。筆者はこの事態を好転させる切り札として「共創型金融」をお勧めしています。
「そうか、金融機関に『事業計画の信ぴょう性などにこだわらず、中小企業を救わないと自分の身も危なくなるぞ』と啓もうしてくれるのだな。」
残念ながら、それは違います。「金融機関が『その事業計画なら実現でき、成果を出せるだろう。あなたの会社が再び元気になり、地域やサプライチェーンの活性化にも繋がるだろう。そういう話なら融資できる』と言える事業計画を描きましょう」との提案です。
「しかしながら、今まで作成した事業計画には納得してもらえなかった。どうしたら、納得してもらえるようになるのか?」今までは単独型「答え(ソリューション)は自社にある」型の事業計画だったと思います。遊休資産を処分して現金化、冗費を削ってコスト削減、あるいは営業マンにもっと働いてもらって販路開拓をするなどです。
しかしこれらアプローチではここ数年、成果が出なかった企業は何ができるか?「今まで以上に努力する」計画には、金融機関はイエスと言いにくいでしょう。遊休資産・冗費は対応済み、営業マンも目一杯働いているなら、これ以上の上積みは期待しにくいのです。
まだ使っていなかった奥の手:共創
新コラムでは「視点を変えましょう」と提案します。答えは確かに社内にありますが、取組みは社内で完結しません。社内でどんなに頑張っても、社外に売らなければ価値は生まれないからです。
こう考えると会社活性化のポイントは、外部との関係の中にあると分かります。
今までは「自分が良いと考えた製品やサービスを提供、買ってもらう」でした。あるいは「自分が良いと考えた生産方法で作る、売り方で売る」でした。
それらをもし「顧客と共同して希望する製品やサービスを提供する」、「関係者の協力を得ながらもっと効率的に製造する」、「顧客や関係者と協力して魅力的かつ便利な販売法を実現する」ができると、業績は飛躍的に向上できる可能性があります。そうやって「なるほど、これなら実現しそうだ」と考えられる計画を策定するのです。
以上のように考えると、企業が生き残り活性化していくポイントは事業性評価から「価値の共創」にシフトしていると分かります。必要なのは共創型「他と共同・協働して今までなかった価値を創造すると見せる(ビジョン)事業計画」です。
これを皆さんと考えたく、新しいコラムシリーズをスタートさせた次第です。
本コラムの印刷版を用意しています
本コラムでは、印刷版を用意しています。印刷版はA4用紙一枚にまとまっているのでとても読みやすくなっています。印刷版を利用して、是非、資金調達する方法をしっかりと学んでみてください。
【筆者へのご相談等はこちらから】
https://stratecutions.jp/index.php/contacts/
<日常営業や事業性評価でやりがいを感じる!企業支援のバイブル>
https://www.amazon.co.jp/dp/B0DYDL46H6/
なお、冒頭の写真はChatGPTにより作成したものです。
プロフィール

落藤伸夫(おちふじ のぶお)
中小企業診断士事務所StrateCutions代表
合同会社StrateCutionsHRD代表
事業性評価支援士協会代表
中小企業診断士、MBA
日本政策金融公庫(中小企業金融公庫~中小企業信用保険公庫)に約30年勤務、金融機関として中小企業を支えた後、事業改善手法を身に付け業務・経営側面から支える専門家となる。現在は顧問として継続的に企業・経営者の伴走支援を行っている。顧問企業には財務改善・資金調達も支援する。
現在は金融機関職員研修も行うなど、事業改善と金融システム整備の両面からの中小企業支援態勢作りに尽力している。
新型コロナウイルス感染症が収束して社会的にも中小企業金融においても「平時」に戻ったとの声がある中、今後は「共創」を目指す企業が躍進していく時代になると確信、全ての中小企業がビジョンを描いて持続と発展を目指すよう提案することとして「共創型金融の時代!あなたはビジョンを描けますか?」コラムを2025年10月からスタートさせた。
【落藤伸夫 著書】
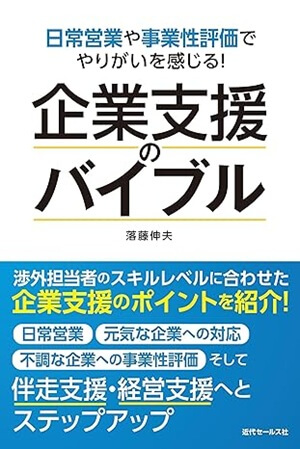
『日常営業や事業性評価でやりがいを感じる!企業支援のバイブル』
さまざまな融資制度や金融商品等や金融ルール、コンプライアンス、営業方法など多岐にわたって学びを続けながらノルマを達成するよう求められる地域金融機関渉外担当者が、仕事に意義を感じながら楽しく、自信とプライドを持って仕事ができることを目指した本。渉外担当者の成長を「日常営業」、「元気な企業への対応」、「不調な企業への対応(事業性評価)」、「伴走支援・経営支援」の5段階に分ける「渉外成熟度モデル」を縦軸に、各々の段階を前向きに捉え、成果を出せる考え方やノウハウを説明する。
Webサイト:StrateCutions













