第4回
社員の悩みは私の悩みと考え“共創”する
StrateCutions (ストラテキューションズ)グループ 落藤 伸夫
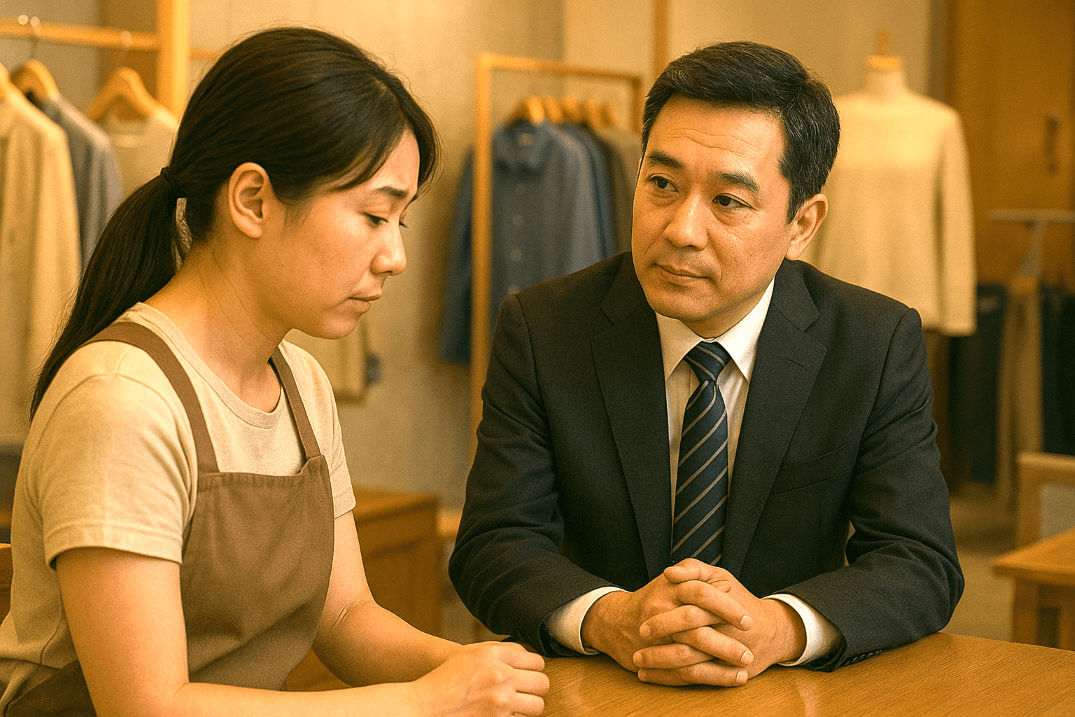
会社は経営者と管理職、そして社員から構成されています。これらの関係をどう捉えるか?多くの場合、対立関係で捉えられます。当たり前だと感じるこの構図を変えることで新たな価値が生まれるかもしれない、今回はこのことについて考えます。
会社における対立構造
職場は会社(経営者・管理職)が方針や目標を打ち出し、社員が方針に従い目標を達成すべく働く、という構図で成り立つ仕組みです。「経営者・管理職=従わせる側」「社員=従う側」という対立構造になりやすいのです。
そして「相手方(カウンターパート)の要求には注意が必要だ、私に負担を負わせることで自分たちが利益を得ようとしているのだから」という認識になりがちです。その想いが表出して「争議」に発展する場合もあります。それほどではなくても、対立の程度は会社ごとに異なりつつも、対立の構図が普遍的と考えられています。
会社ではそれぞれの当事者が悩みを抱えています。経営者は経営上の悩みに加えて個人的な悩みを抱え、管理職はマネジメント上の悩みに加えて個人的な悩みを抱え、社員は職務遂行上の悩みに加えて個人的な悩みを抱えている、という状況です。
経営者・管理職にとって社員が「悩みのタネ」になっている場合が少なくなく、逆に社員にとって経営者・管理職が「悩みのタネ」になっている場合が少なくありません。両者が対立しているという関係性が、ここに現れているのです。
会社が船で、それに乗る仲間と考えてみる
検討の対象を目に見える人だけに限ると上の構図が自然に感じられますが、目に見えない「会社」を船だと考えると、違う構図が見えきます。経営者・管理職と社員は同じ船に乗る仲間だと解釈できるのです。
経営者は進むべき方向を示し舵を取る責任を負う一方で、社員が現場の仕事を遂行して実際に船を動かしている、管理職は社員をマネジメントすると共に経営者をサポートしているという姿です。誰かが欠けると、航行は成り立ちません。経営者と管理職、社員が各々の役割を果たすことで、船は安全かつ経済的に目的地に到達することができます。
このように考えると全ての当事者にとってカウンターパートは敵ではなくなります。船を守り、運航し、経済的な利益を得るには、カウンターパートによる貢献が必要だと理解できるからです。
経営者は「社員の取り分を減らせば会社の取り分を増やせ、経営者・管理職の取り分も増やせる」と考えるかもしれませんが、社員はそれが悩みの原因となり、気持ちが高まって争議に至るかもしれません。すると会社の活動は妨害され、売上や利益が減少します。
「社員は経営者や管理職とは対立しているので、相手のことなど思いやる必要はないのだ」と考えるよりも、「社員も含め、経営者や管理職など各パートが一体になって会社を成り立たせ、事業を行っているのだから、互いの悩みを大きくしないよう思いやった方が、結局は自分のためになる」と思えるようになります。
個人の悩みも「私の悩み」と考えるメリット
こうして「社員にとって経営者・管理職が悩みのタネである」状況が緩和されると、社員は悩みが減少して気持ちよく仕事ができ、パフォーマンスが向上すると考えられます。積極性が増し、喜びをもって仕事ができるので売上が向上、非効率な動きも減って利益が増えるかもしれません。それは会社にとって喜ばしいことです。
一方で社員は健康や介護、子育てなど、個人的な悩みも抱えているでしょう。例えば子育て中の社員は、保育園の都合で残業が困難かもしれません。自分自身、やり残してしまった仕事を同僚に押し付けることも憚られ、板挟みになっているかもしれません。
経営者にとっても「規則もあるし、他の人とのバランスもあるから」と板挟みになって二進も三進もいかないかもしれません。
では放置するしかないのか?先ほども考えたように、全てのパートで「悩み」が解消に向かうと、それは会社にとってメリットになると考えられます。個人の悩みとて同じでしょう。
であるなら「それは社員の(管理職の・経営者の)個人的な悩みだから私には関係ない」と考えるのではなく「私の悩みでもある。カウンターパートの悩みを解決すれば、私の悩みも減少する」と考えた方が、望む境地に至れる可能性が高まります。
社員との「共創」を考える価値があるのです。
本コラムの印刷版を用意しています
本コラムでは、印刷版を用意しています。印刷版はA4用紙一枚にまとまっているのでとても読みやすくなっています。印刷版を利用して、是非、資金調達する方法をしっかりと学んでみてください。
【筆者へのご相談等はこちらから】
https://stratecutions.jp/index.php/contacts/
<日常営業や事業性評価でやりがいを感じる!企業支援のバイブル>
https://www.amazon.co.jp/dp/B0DYDL46H6/
なお、冒頭の写真はChatGPTにより作成したものです。
プロフィール

落藤伸夫(おちふじ のぶお)
中小企業診断士事務所StrateCutions代表
合同会社StrateCutionsHRD代表
事業性評価支援士協会代表
中小企業診断士、MBA
日本政策金融公庫(中小企業金融公庫~中小企業信用保険公庫)に約30年勤務、金融機関として中小企業を支えた後、事業改善手法を身に付け業務・経営側面から支える専門家となる。現在は顧問として継続的に企業・経営者の伴走支援を行っている。顧問企業には財務改善・資金調達も支援する。
現在は金融機関職員研修も行うなど、事業改善と金融システム整備の両面からの中小企業支援態勢作りに尽力している。
新型コロナウイルス感染症が収束して社会的にも中小企業金融においても「平時」に戻ったとの声がある中、今後は「共創」を目指す企業が躍進していく時代になると確信、全ての中小企業がビジョンを描いて持続と発展を目指すよう提案することとして「共創型金融の時代!あなたはビジョンを描けますか?」コラムを2025年10月からスタートさせた。
【落藤伸夫 著書】
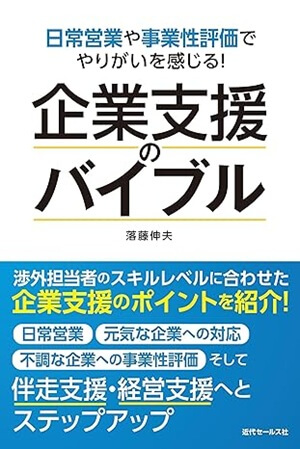
『日常営業や事業性評価でやりがいを感じる!企業支援のバイブル』
さまざまな融資制度や金融商品等や金融ルール、コンプライアンス、営業方法など多岐にわたって学びを続けながらノルマを達成するよう求められる地域金融機関渉外担当者が、仕事に意義を感じながら楽しく、自信とプライドを持って仕事ができることを目指した本。渉外担当者の成長を「日常営業」、「元気な企業への対応」、「不調な企業への対応(事業性評価)」、「伴走支援・経営支援」の5段階に分ける「渉外成熟度モデル」を縦軸に、各々の段階を前向きに捉え、成果を出せる考え方やノウハウを説明する。
Webサイト:StrateCutions












