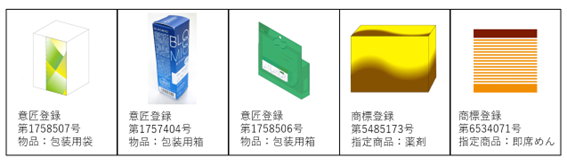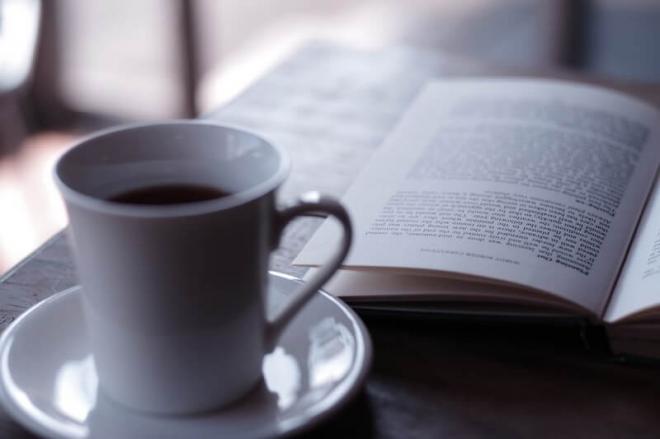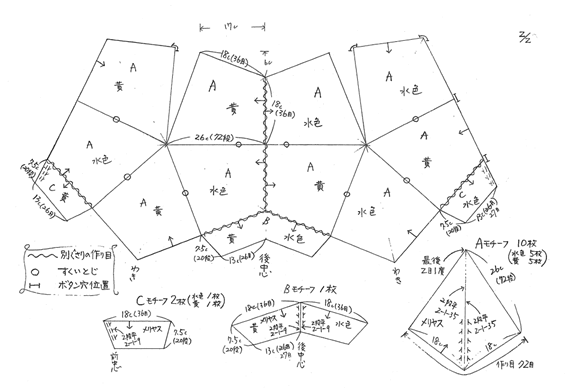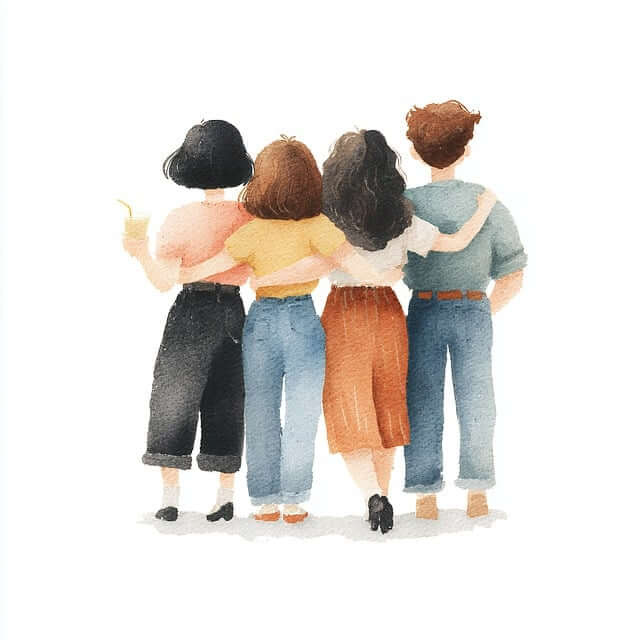新聞記事って社内だけなら共有しても大丈夫?
はじめに
情報化社会において簡単に素早く、社内で情報共有することは企業にとっても重要ですが、皆さんの会社では、日々の経済ニュースや業界の動向などを社員同士でシェアするために、例えば新聞紙面をコピーして社内で回覧したり、PDF化して共有フォルダに格納したり、はたまたイントラネットに掲載したり…などなどしていませんか?
「営利目的ではないから問題ない」、「社内だけだから大丈夫」、という思いでついやってしまっているかもしれないその行為、実は著作権法上問題となる場合があります。
今回は、新聞記事の社内共有について、著作権法上の問題点を見ていきましょう。

新聞記事の著作物性について
著作物の例として、著作権法では小説や脚本、音楽や絵画などが挙げられています。これらについては「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」としてイメージがしやすく、「ほんとに著作物なの?」という疑問は持たれないのではないかと思います。
ところが新聞記事については、上記の例示には含まれていません。また同法では、事実の伝達にすぎない雑報や時事の報道は著作物に該当しないと規定されていて、新聞記事がこれに該当するようにも思われるため、「新聞記事って著作物なの?」と疑問を持たれる方もいらっしゃるかもしれません。それでは新聞記事は著作物と言えるのでしょうか。
過去の裁判例
著作権侵害訴訟の中で新聞記事の著作物性が争われた事件として、(1)知財高判令和5年6月8日(令和5年(ネ)第10008号)、(2)知財高判令和5年6月8日(令和4年(ネ)第10106号)があります。これは、新聞記事を画像データにして保存し、社内のイントラネット上にアップロードして従業員等が閲覧できる状態に置いた被告の行為が著作権侵害にあたるとして、大手新聞社2社から損害賠償請求がなされた事件です。
2つの事件の中で被告は、自らが画像データにした各新聞記事は事実を伝達するものにすぎず、文章表現もありふれているなどとして著作物性を否定する旨の主張をしましたが、(1)の事件では裁判所は、「本件各記事において、記事内容を分かりやすく要約したタイトルが付され、文章表現の方法等について表現上の工夫が凝らされていることは原判決認定のとおりである…(中略)…記載内容の取捨選択がされ、記者の何らかの創造性が顕れており、著作物であると認められる。本件各記事は、法10条2項にいう『事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道』とはいえない」と判断しています。
また、(2)の事件では裁判所は、「…相当量の情報について、読者に分かりやすく伝わるよう、順序等を整えて記載されるなど表現上の工夫をし、それ以外の記事については、いずれも、当該記事のテーマに関する直接的な事実関係に加えて、当該テーマに関連する相当数の事項を適宜の順序、形式で記事に組み合わせたり、関係者のインタビューや供述等を、適宜、取捨選択したり要約するなどの表現上の工夫をして記事を作成していることが認められ、各記事の作成者の個性が表れており、いずれも作成者の思想又は感情が創作的に表現されたものと認められるものであり、『事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道』であるということはできない。また、著作物といえるための創作性の程度については、高度な芸術性や独創性まで要するものではなく、作成者の何らかの個性が発揮されていれば足り、報道を目的とする新聞記事であるからといって、そのような意味での創作性を有し得ないということにはならない。」と判断しています。
これらの裁判例からは、新聞記事の中でも例えば死亡記事等の、死亡した人の氏名や簡単な経歴、葬儀の日時や場所といった事実関係を単純に記述したに過ぎない記事については著作物性がないと言えますが、記者や編集者による表現上の工夫が凝らされ、個性が表れている記事については著作物性が認められると言えそうです。
「社内限定」であれば著作物の複製(コピー)はOK?
それでは、「社内限定での情報共有」を目的とするものであれば、著作物を無断で複製しても問題はないのでしょうか。結論は、「ノー」です。著作権法では、「著作物は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。」という、いわゆる「私的使用のための複製」を定めた規定があり、私的使用を目的とする著作物の複製(コピー)が、一定の場合を除いて認められています。どこまでが「家庭内その他これに準ずる限られた範囲内」と判断されるかはケースバイケースですが、少なくとも社員等への情報共有のために社内で新聞記事をコピーする行為は、この範囲内での複製とはいえないため注意する必要があります。
「私的使用のための複製」については「著作権侵害にならない『私的使用』の限界はどこか」で詳しく説明されていますので、ご参照下さい。
「非営利目的」であれば著作物の複製(コピー)はOK?
社内での情報共有のために新聞記事をコピーする行為は営利目的ではないようにも思われますが、著作権法上、「非営利目的」であれば著作物を複製しても問題はないのでしょうか?これも結論としては「ノー」です。著作権法では、一定の場合に著作物を自由に利用することができる、いわゆる権利制限規定が定められています。上述した「私的使用のための複製」もその一つです。権利制限規定の中には、例えば営利を目的とせず、聴衆や観衆から料金を受け取らず、上演・演奏等する人に報酬を支払わない場合は、著作物を公に上演・演奏・上映・口述することができると規定されているものもありますが、この中に著作物を複製(コピー)する行為は含まれていません。つまり営利目的であっても非営利目的であっても、著作権者に無断で著作物を複製(コピー)する行為は、その他の権利制限規定で定められた行為以外は著作権(複製権)侵害となり得る点に注意する必要があります。
なお、上述の「私的利用のための複製」や「営利を目的としない上演等」に関する権利制限規定では、要件を満たした「複製」や「上演・演奏・上映・口述」を自由に行うことができる旨が規定されていますが、社内外のイントラネットやインターネット上に著作物をアップロード(公衆送信)行為については適用されませんので、この点にもご注意が必要です。
最後に
新聞記事は事実の集まりだからと自由に利用できると思われがちですが、実際には著作権で保護されている著作物ですので、たとえ社内にとどめた非営利目的だとしても、新聞記事を著作権者に無断でコピーしてシェアする行為は著作権侵害に当たることを上記でご説明しました。
新聞記事を切り抜いて、社内でも人通りの多い、目立つ場所に設置された掲示板に貼る等の昔ながらの共有方法であれば著作権法上の問題はないと思われますが、他の営業所や支店の社員との情報共有ができないこともあり、そのような方法は今の時代にはあまり効果的ではないかもしれません。
安心して正しく新聞記事を社内共有するには、やはり新聞社や著作権管理団体と利用契約を結ぶことをお勧めします。
令和7年度 日本弁理士会著作権委員会委員
弁理士 瀬川 左英
※ この記事は執筆時の法令等に則って書かれています。
※ 著作権に関するご相談はお近くの弁理士まで(相談費用は事前にご確認ください)。
また、日本弁理士会各地域会の無料相談窓口でも相談を受け付けます。以下のHPからお申込みください。
- 北海道会https://jpaa-hokkaido.jp/conferences/
- 東北会https://www.jpaa-tohoku.jp/consultation.html
- 北陸会https://www.jpaa-hokuriku.jp/consult/
- 関東会https://www.jpaa-kanto.jp/consultation/
- 東海会https://www.jpaa-tokai.jp/activities/consultation/index.html
- 関西会https://www.kjpaa.jp/beginner/consul
- 中国会https://www.jpaa-chugoku.jp/activity/
- 四国会https://jpaa-shikoku.jp/consult/
- 九州会https://www.jpaa-kyusyu.jp/sodankai/