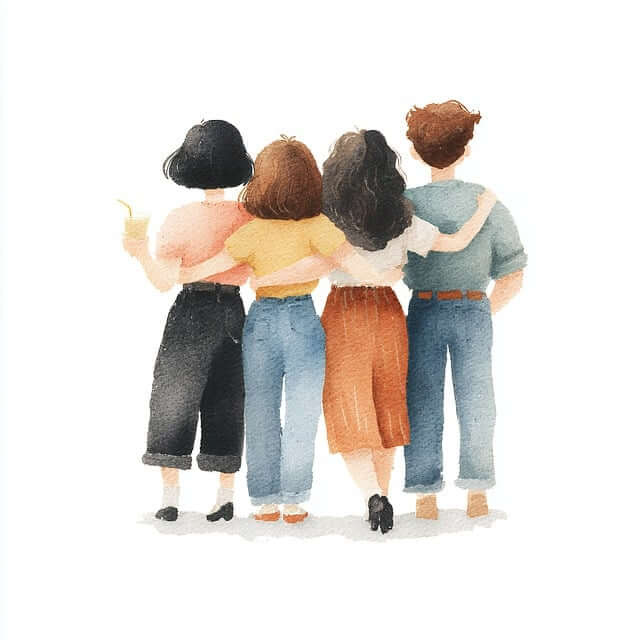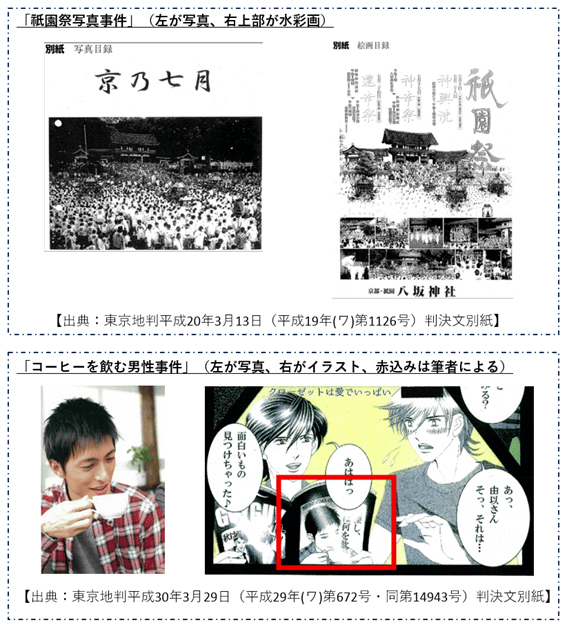音楽のサンプリング、著作権はOK?NG?弁理士が解説

サンプリングとは?
音楽におけるサンプリングとは、サンプラーという機材やPCを使い、既存の楽曲や自然の音(川のせせらぎ、人の声など)を録音(サンプリング)し、それらを素材として自らの楽曲制作に利用する手法のことです。
他人の楽曲をサンプリングする場合、その楽曲には著作権が存在します。個人で楽しむため(私的利用)であれば問題ありませんが、楽曲を公開・販売するとなると、法的な問題が関わってきます。
日本におけるサンプリングと権利関係
日本で他人の音源を無断でサンプリングした場合、主に「著作権」と「著作隣接権」という2つの権利が問題となります。
著作権
作曲家や作詞家が持つ、楽曲そのものに対する権利です。 無断でサンプリングを行うと、元の楽曲をコピーすることになるため「複製権」の侵害にあたる可能性があります。 また、サンプリングした楽曲をライブで演奏すれば「演奏権」、インターネットで配信すれば「公衆送信権」の侵害となる可能性があります。 これらの権利は、JASRACやNexToneといった著作権等管理事業者に所定の手続きを行うことで、許諾を得られます(著作権者自らが管理している楽曲を除く)。
ただし、著作権が保護するのは「創作的な表現」です。そのため、サンプリングした部分がごく短かったり、ありふれたフレーズであったりして「創作性がない」と判断されれば、著作権侵害には当たらない可能性もゼロではありません。
著作隣接権
著作権の問題に加え、サンプリングでは「著作隣接権」を考慮する必要があります。 楽曲をレコーディングした、いわゆる原盤について、その製作に貢献した「レコード製作者(レコード会社など)」 と 「実演家(歌手や演奏者)」 にそれぞれレコード製作者の権利と実演家の権利が認められています。
著作隣接権は、著作権と違って音に創作性があるかどうかを問いません。 そのため、法律上はほんのわずかな時間でもサンプリングすれば、レコード製作者の「複製権」や実演家の「録音権」などを侵害することになります(私的利用を除く)。 この権利の許諾を得るには、JASRAC等の著作権等管理事業者ではなく、音源の権利を持つレコード会社等(原盤権者)へ直接連絡する必要があります。原盤権者が実演家の権利も含めて管理している場合が通常です。
現状、日本では「ごくわずかなサンプリング」や「加工したサンプリング」がどこまで許されるかを示した裁判例がありません。そのため、実務上は「サンプリングをするなら、必ず原盤権者の許諾が必要」と考えておくのが最も安全です。
海外の裁判例ではどう判断されている?
日本では明確な司法判断がありませんが、海外ではサンプリングに関する有名な裁判がいくつかあります。ここでは、アメリカとEUの裁判を見てみましょう。
【米国】わずかでも侵害とした判決 Bridgeport Music v. Dimension Films事件(2005年)
ヒップホップグループN.W.A.の楽曲が、Funkadelicというバンドのギターフレーズをサンプリングしたとして訴えられました。 裁判所(第6巡回区控訴裁判所)は、「たとえごくわずかなサンプリングであっても許諾が必要」と判断しました。 この判決は音楽業界に衝撃を与え、アーティストがサンプリングの利用をためらう一因になったとも言われています。 (参考:米国では音源は著作隣接権ではなく、サウンドレコーディング著作権として保護されます)
<参考音源>
● サンプリング元: Funkadelic - Get Off Your Ass and Jam
● サンプリングを使用した曲: N.W.A. - 100 Miles and Runnin'
● 元の曲の冒頭で鳴っているギターフレーズが、N.W.A.の曲の1:08や2:09あたりで、背景に薄く流れているのが分かります。
【米国】わずかなら侵害ではないとした判決 VMG Salsoul v. Ciccone事件(2016年)
今度は、マドンナの世界的ヒット曲「Vogue」が、Salsoul Orchestraの楽曲からブラス音をサンプリングしたとして訴えられました。 しかし、こちらの裁判所(第9巡回区控訴裁判所)は、サンプリングされた部分がごくわずかであるとして、著作権侵害を認めませんでした。 これは先のBridgeport事件とは正反対の判断であり、米国内では司法判断が分かれている状況です。
<参考音源>
● サンプリング元: The Salsoul Orchestra - Ooh, I Love It (Love Break)
● サンプリングを使用した曲: Madonna - Vogue (Official Video)
● 元の曲の4:39や4:43あたりで鳴る「ポワッ」というブラスヒットの音が、マドンナの曲の0:55や1:02などで使用されています。
【EU】「耳で識別できるか」を基準とした判決 Pelham事件(2019年)
電子音楽のパイオニアであるクラフトワークの楽曲がサンプリングされた事件です。 この事件でEU司法裁判所は、原則としてサンプリングは複製権侵害にあたるとしつつも、重要な例外を示しました。それは、サンプリングした音源を、元の音源だと「耳で識別できない」ように加工して新たな作品で使用する場合は、複製権侵害にはあたらない、という判断です。 これは、すべてのサンプリングを違法とするのではなく、「元の音源が分かるかどうか」というリスナーの感覚を基準にした点で評価されます。
<参考音源>
● サンプリング元:Kraftwerk -Metall auf Metall
● サンプリングを使用した曲:Sabrina Setlur - Nur Mir
● 元の曲の0:36からの左チャンネル→右チャンネルにパンニングされているパーカッションパターンが、"Nur Mir"冒頭から全編に渡って使われています。
【まとめ】
音楽のサンプリングは、クリエイティブな表現手法である一方、権利関係が非常に複雑です。今回のポイントをまとめます。
● 日本では、裁判例が乏しく明確な基準がないため、原則として楽曲の著作権者及び音源の権利者(レコード会社など)の許諾が必須。
● 問題となるのは「著作権(楽曲)」と「著作隣接権(録音された音そのもの)」の2つであり、特に後者は創作性を問わないため、ごく僅かなサンプリングでも権利侵害にあたります。
● 米国では司法判断が分かれており、「わずかでもNG」とした判例と「ごくわずかならOK」とした判例が対立している。欧州では「原曲と識別できなければOK」という判断が示されています。
サンプリングを用いた楽曲制作を検討している方は、安易に判断せず、事前に専門家である弁理士に相談することをお勧めします。
令和7年度 日本弁理士会著作権委員会委員
弁理士 瀬戸口 克
※ この記事は執筆時の法令等に則って書かれています。
※ 著作権に関するご相談はお近くの弁理士まで(相談費用は事前にご確認ください)。
また、日本弁理士会各地域会の無料相談窓口でも相談を受け付けます。以下のHPからお申込みください。
- 北海道会https://jpaa-hokkaido.jp/conferences/
- 東北会https://www.jpaa-tohoku.jp/consultation.html
- 北陸会https://www.jpaa-hokuriku.jp/consult/
- 関東会https://www.jpaa-kanto.jp/consultation/
- 東海会https://www.jpaa-tokai.jp/activities/consultation/index.html
- 関西会https://www.kjpaa.jp/beginner/consul
- 中国会https://www.jpaa-chugoku.jp/activity/
- 四国会https://jpaa-shikoku.jp/consult/
- 九州会https://www.jpaa-kyusyu.jp/sodankai/