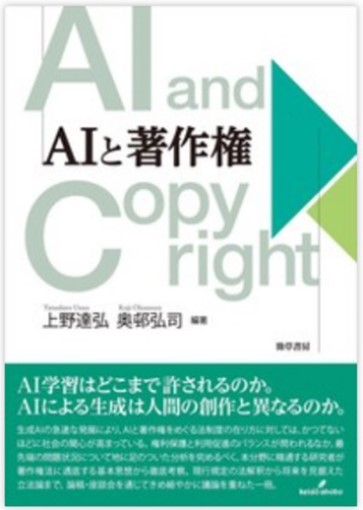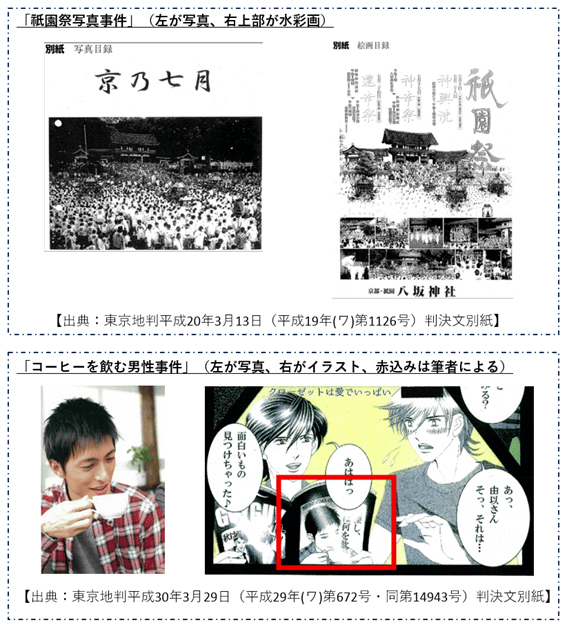先輩からのお願いであっても遠慮せずに明確な合意形成を!~ 段ボール芸人事件~
はじめに
先輩からのお願いって、嫌なときもあれば、自分が信頼されているようで嬉しいときもあります。しかし、いざ引き受けたとしても、その後のやり取りの中で先輩からの注文に反対するのは難しく、自分の意見を主張するのは勇気が要ります。つい、先輩の思う通りに約束させられ、そのまま、ずるずると物事が進んでしまうことがあります。
本事件「段ボール芸人事件」は、ある後輩芸人が気を遣いすぎてしまい、先輩芸人に対して自らの権利を行使できなかった事案です(知財高判令和6年(ネ)第10079号)。

事件の概要
Xは、演芸家としてYの6年後輩に当たります。Yは、段ボールで制作された小道具を使用するコントなどの演芸を実演する演芸家です。
Xは、Yからの依頼に応じて平成26年9月から令和3年2月頃までYの演芸のための小道具を制作し、Yは、これらの小道具を自らの演芸で使用しました。
Xは、小道具の制作者(著作者)として自らの名前を公表するようにYに要求しましたが、なかなか応じてもらえませんでした。
そこで、Xは、Yが著作者名を公表しなかったことが著作者人格権の1つ、氏名表示権侵害に当たると主張し、慰謝料500万円およびYのX(旧Twitter)アカウントでの謝罪文の掲載などをYに対して請求し、東京地裁へ提訴しました。
しかし、東京地裁はXの請求を棄却し、知財高裁はXの控訴を棄却しました。
氏名表示権
氏名表示権(著19条)は、著作物の著作者に与えられる、著作者の人格的な利益を保護する著作者人格権(著18条~20条)の1つであって、著作物を公衆へ提示したり提供したりする際に著作者名の表示をどのようにするかを決めることができる権利です。著作者自らの実名を表示したり、変名(ペンネーム、芸名など)を表示したり、匿名にしたりすることができます。
著作物の利用者は、原則として著作者の希望に沿わなければなりませんが、氏名表示権の不行使の契約を著作者との間で成立させれば、著作者名を表示することなく著作物を利用することができます。
このような不行使契約がXとYとの間で成立していたか否か、成立していたとすれば、いつ、それが終了して著作者名の表示の同意が成立したのかが、本事件の最大の注目ポイントです。
裁判所の判断
XとYとのやり取りを時系列順に追いながら、XとYとの間でなされた契約や合意を知財高裁がどのように判断したのかを見ていきます。
(1)平成25年8月頃~令和2年5月頃のやり取り
Yは、平成25年8月頃から、自らの演芸で使う小道具の制作をXへ依頼し、Xは、令和2年5月頃までに約100点の小道具を制作してYへ引き渡しました。Yは、平成26年9月から令和2年5月頃までの期間、制作者名(著作者名)に言及することなく、Xが制作した小道具を自らの演芸で使用しました。各小道具につき5千円~1万円程度をXへ支払いました。
平成25年8月頃、Yは、後輩に小道具を作らせていることを他の演芸家からイジられると困るのでXが小道具を制作した事実を(少なくともしばらくは)公表しないで欲しい旨をXへ伝えました。Xは、この時点ではYの要請を否定しない返答をしました。
Xは、令和2年5月頃まで、小道具をYへ提供し続けたり、一部の小道具について制作および提供を自ら申し出たり、Xが小道具を制作している事実を関係者に知られたくないとのYの意向に配慮したりしました。
知財高裁は、これらの事実を踏まえて、平成25年8月頃に氏名表示権の不行使の契約が成立しており、令和2年5月頃まではそれが有効であったと、認定しました。
なお、Xは、小道具を提供し続けたのは厳しい上下関係やYからの圧力があったからだと主張しました。しかし、知財高裁は、Xが先輩Yに対する遠慮があったことを認めたものの、「原告の意思が不当に抑圧されていたりしていたと窺われるまでの事実は認められない」との理由で、Xの主張を退けました。
(2)XからYへの久々の連絡
Yは、令和2年6月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響もあり、Xに小道具の制作を依頼していませんでしたが、同年10月20日、Xへ「また、ぜひともお頼みごともさせていただきたいです」などのLINEメッセージを送信しました。
Xは、同月24日、Yの言動に対する不満のほか「今小道具の会社を立ち上げたところで、アドバイザーの方から権利関係のことは厳しく言われるので、僕が作ってない話になるものは、製作を控えさせてください。」などのLINEメッセージをYへ送信しました。
同月27日、Yが発起してXとLINE通話で会話し、翌日以降のLINEメッセージのやり取りが以前と同様の親しげな内容のものとなりました。
知財高裁は、10月のこれらのやり取りや後述の跳び箱の小道具に関するやり取りを根拠に、遅くとも令和3年2月頃までには氏名表示権の不行使の契約が解除され、Xが今後制作する小道具をXが制作した事実をYが公表する旨の約束がなされていたと、推認しました。
(3)跳び箱の小道具に関するやり取り
Yは、令和3年2月15日、自らの演芸に使用する小道具(跳び箱)の制作をXへ依頼し、Xは、この小道具を制作しました。
この小道具のデザインや引渡しに関するLINEメッセージのやりとりの中で、Xは、Xが制作者であることの公表を検討するようにYへ促し、Yは、「Xのお言葉分かるから、きちんと踏まえて考えさせてください。」と返信しました。
後日、Xは、今回の小道具の作成者をX自ら発表してもよいかをYに問い合わせ、Yは、これを一旦保留して改めて連絡する旨を伝え、Xは、一応、同意しました。
Yは、この小道具を使用した自らの演芸の動画を配信し、Xは、この配信動画を観た後、Yに対して「クリエーターとしては我慢できない」、「Yは著作権をあまりにも軽視しすぎている」、「存在価値が否定されていて本当につらい」など自らの気持ちを伝えた上で、「今回の跳び箱で対応していただけないようなら 〔1〕今後Yさんの小道具は作らない。〔2〕どなたかに今までのやりとりを相談します。(まだ決まってませんが、弁護士とか雑誌記者の可能性も考えてます。)」とのLINEメッセージを送信しました。
すると、Yは、同日中に自らのツイッターアカウント上に、「今回の単独ライブにて出てきた小道具の中で、「跳び箱」がありましたが、あの、スペシャル素敵跳び箱…後輩のXにご依頼させていただき、作ってもらいました(涙)」と投稿しました。
この投稿による制作者名の発表がXとYとの間の同意の内容に合っているか否かも、注目ポイントの1つです。配信動画であれば、制作者名をアナウンスしたりテロップで表示したりことができます。しかし、この配信動画にはそのような処理が施されておらず、上述の通り、配信後にYが自らのツイッターアカウントにて制作者名を公表しました。
知財高裁は、Xの供述および陳述書の内容に基づいて「原告が被告に求めていたと述べているのは、原告自身がツイッターで発表すること、又は被告がツイッターなどで事後に発表することであって、被告演芸そのものの場において表示等をすることではない。」と理由付けして、跳び箱についての約束が果たされたと認定しました。
(4)まとめ
平成25年8月頃~令和2年5月頃に制作された小道具については、氏名表示権の不行使の契約が有効であり、氏名表示権の侵害がなかったと判断されました。
令和3年2月に制作された跳び箱の小道具については、制作者名(著作者名)の公表について合意されたものの、その合意内容は、XまたはYのツイッターアカウントでの発表であって、現にYがそのように発表したことによって合意の内容の通りに約束が果たされたと判断されました。
最後に
手が先輩であったとしても、遠慮せずに合意を得ることが必要です。知財高裁が「原告が被告に対し、小道具の制作者が原告であること(少なくとも、実際の制作に関与していること)の公表を求めたことは相当回数あったと認められるが、被告はその度に言葉巧みに拒絶し、だからこそ原告は様々な言い方で提案を繰り返してきたとみるのが相当であって…被告が公表する合意に至ったことを認めるに足りない。」と判断した通り、自らの意思を伝えることができても相手の態度があやふやなままであれば、合意が得られたことになりません。
合意内容が明確であることも重要です。曖昧であれば、約束が果たされたか否かで争いになり得ます。
一方、力が強い側の者は、相手の要求に対して曖昧な態度で居続けると、相手の怒りを爆発させてしまいます。法律的に問題がないとしても、相手からの信頼を失い、ダークなイメージが付いてしまいます。早い時期から相手の気持ちを汲み、しっかりと話し合うべきです。
この記事が「ためになったねー」や「ためになったよー」と読者の皆様に思って頂けると嬉しいです。
令和7年度 日本弁理士会著作権委員会委員
弁理士 坂田 泰弘
※ この記事は執筆時の法令等に則って書かれています。
※ 著作権に関するご相談はお近くの弁理士まで(相談費用は事前にご確認ください)。
また、日本弁理士会各地域会の無料相談窓口でも相談を受け付けます。以下のHPからお申込みください。
- 北海道会https://jpaa-hokkaido.jp/conferences/
- 東北会https://www.jpaa-tohoku.jp/consultation.html
- 北陸会https://www.jpaa-hokuriku.jp/consult/
- 関東会https://www.jpaa-kanto.jp/consultation/
- 東海会https://www.jpaa-tokai.jp/activities/consultation/index.html
- 関西会https://www.kjpaa.jp/beginner/consul
- 中国会https://www.jpaa-chugoku.jp/activity/
- 四国会https://jpaa-shikoku.jp/consult/
- 九州会https://www.jpaa-kyusyu.jp/sodankai/