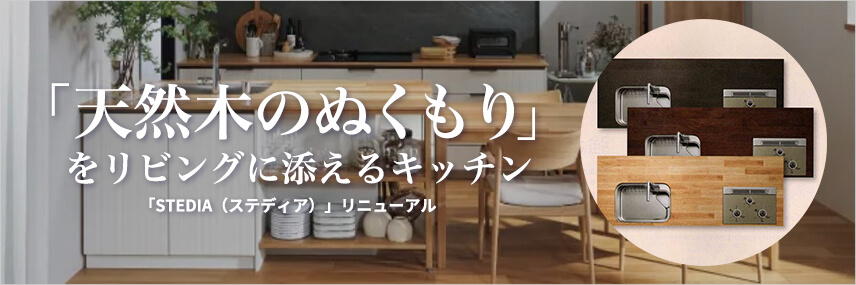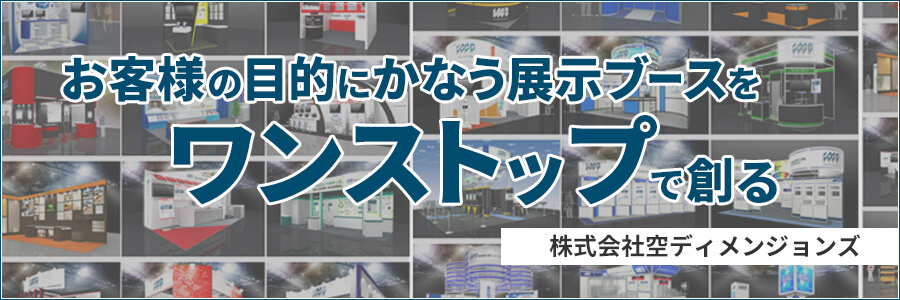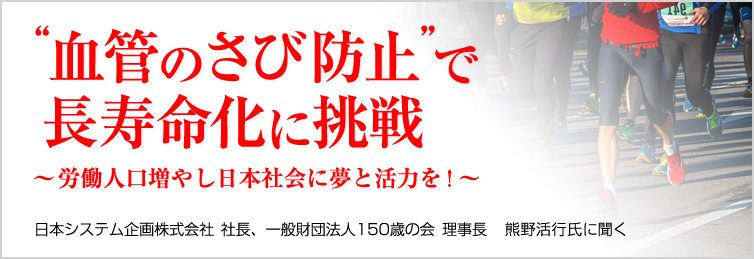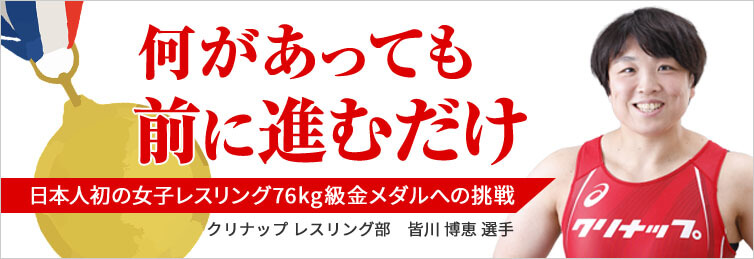成長戦略や事業承継にM&A(合併・買収)を選択する中小企業が増えている。一方でM&A市場の健全な発展には、売り手と買い手をつなぐ支援機関への高い信頼が欠かせない。その一翼を担うのがM&Aコンサルティングだ。売り手と買い手のどちらか一方のアドバイザーとして寄り添い、統合効果を最大限発揮できる態勢が整うまでサポートを惜しまない。こうして築いた顧客の信頼をベースに、改めてM&Aの本質、つまり双方が満足する「ホワイトM&A」に力を注ぐ。
買い戻し条項を入れることで双方が折り合いやすくなり、M&Aがもっと一般化する
 株式会社M&Aコンサルティング
株式会社M&Aコンサルティング
代表取締役 髙野健二氏
髙野健二代表取締役はホワイトM&Aに注力する理由をこう語った。買い戻し条項とは、売買契約を締結する際にあらかじめ決めた条件が守れない場合、売り手が買い戻す特約だ。売り手が譲渡時に気に掛ける従業員や取引先といったステークホルダー(利害関係者)を守るのに有効という。
条件交渉の中で売り手が重要視するのは譲渡価格に加え、従業員の待遇維持や取引先との関係継続だ。とはいえ、こうした条件を買い手が無条件で受け入れるわけもなく、合意のために従業員や取引先の維持を優先し、譲渡価格を引き下げても構わないという売り手は少数だが出てきている。買い手も安く買えるので、従業員と取引先を守ると約束する。
しかし、企業文化の違いなどから、買い手が「仕事のやり方を変える」などといって一方的に自社の意向や方針を押し付けて約束を破ることもありうる。売り手の反発を買い、欲しかった人材も離反するので統合効果を期待するのは難しい。「こんなはずでなかった」「売らなければよかった」と悔やまないためにも、買い戻し条項付きM&Aを選択するようになる売り手も出てくるとみる。

一方、買い手は買い戻し条項を受け入れることで、ステークホルダーを大切にするというメッセージを発信できる。売り手にとって、譲渡後も信用して任せられる魅力的な企業と映るからだ。従業員からも歓迎されモチベーションが上がり、取引先の信頼も高まる。それだけ統合効果を早期に発揮できるようになるわけだ。
買い戻し条項を入れることで、双方が満足できるホワイトM&Aが実現する。相互補完による事業成長とそれに伴う企業価値の最大化をもたらし、ひいては日本経済の活性化につながり、産業の新陳代謝をもたらす。
売り手と買い手のどちらか一方のアドバイザー(FA=ファイナンシャルアドバイザー)として寄り添う
M&Aアドバイザリー業務を手掛ける支援機関は、売り手と買い手の双方と契約して成立を促す仲介業者が圧倒的に多い。日本特有で、欧米では手掛けないのが常識という。高く売りたい売り手と、安く買いたい買い手の双方から依頼を受けるだけに利益相反を招きかねないからだ。「あちらを立てればこちらが立たず」というわけだ。リピーターになりうる買い手側に立ってM&Aをまとめる動機も働く。逆に、売り手の利益を優先して隠したい情報を出さずにまとめることもありうる。
これでは市場の公平性を損ないかねない。だからこそFA専業が少ない中でも、髙野氏はFAにこだわってきた。このため、徹底した顧客ファーストを実践。相手企業の価値やリスクを事前に調査・評価するデューデリジェンスも、M&A成立後の統合プロセスであるPMIも全力を尽くす。中でも、統合効果をもたらす最大要因といえる従業員の雇用と待遇の維持に厳しい目を向ける。「従業員を大切にしない、言い換えると安心して働けないM&Aはうまくいかない」ことを知っているからだ。

このため、M&Aの本質にフォーカスをあてる。売り手には譲渡条件の優先順位を、買い手には目的の明確化を求める。これにより相互が理解し利害が一致、満足できるM&Aに近づくからだ。そのために「時間をかけて粘り強く説明し、互いに歩み寄ることで納得を得る」ことに全力を注ぐ。失敗しないための心得だ。
こうした「顧客ファーストのFA」が市場から認知され、M&Aを考える企業からの問い合わせも増えている。髙野氏は「2~3カ月で1件のペースだったが、最近は週に2~3件」という。M&A成立後がむしろ本番といわれるなか、PMIの重要性を理解する企業が増えているのも追い風だ。こうして顧客の信頼を獲得していった。
依頼をしっかりこなすことで案件が途切れなく来るようになった
設立は2016年6月。今年で10年目に突入した。顧客に寄り添う戦略が支持され事業は軌道に乗り、金額、件数とも安定。継続的にアドバイザリーを務めるため採用した固定報酬をベースに、成功報酬が上乗せされる格好で収益は伸び、経営は順調に推移している。
このうち成功報酬が売り上げの約6割を占める。案件は常に5~10件程度あって並行的にこなしている。それだけM&Aが一般化してきたといえ、案件の進捗状況はまちまちだが、年間2~3件程度のM&Aを成功に導く。成功報酬でもリピーターは多く、信頼の高さが伺える。一方の固定報酬は4社。成長の手段としてM&Aを恒常的に検討している企業が多く、PMIを踏まえた案件の紹介・交渉アドバイスを担う。
一生の仕事にたどりつけた
M&Aアドバイザリー業務について髙野氏は間髪入れずこう答えた。一方で「泥臭い仕事」ともいう。M&Aの合意に向けた選択肢を提案しても決断するのはFA契約を結んだ依頼主であり、報われるとは限らない「もどかしさ」を抱えながらアドバイスを送る。
このため、いろいろな人に会い、話しを聞いて情報を収集する。情報がすべての世界であり、アドバイザーとして選ばれる「種まき」に直結するからだ。中小企業同士のM&Aでも国内外の政治情勢や経済状況、例えば米トランプ大統領の言動が世界に与える影響や人口減少の日本がとる外国人受け入れ問題がどうなるかを考えて助言する。
「決して金儲けにはいかない」とも強調する。依頼主の目的に沿わないと判断したら躊躇なく交渉の打ち切りや他のスキームへの変更を勧める。M&Aコンサルと相性が悪いと考えるIPO(新規株式公開)も念頭にない。仕事が面白いからで、75歳(今は55歳)まで続けるという。これまでの10年間で「自分の思うアドバイザリー業務が行えるようになった」と実感。その手応えをもとに、今後10年間は「魂を入れるとともに気を引き締めて」案件をこなし、コミュニケーション能力を磨く。引き出し(経験)を増やすためだ。やりたかった仕事にたどり着いたという自負と責任が、売り手と買い手の双方が後悔しないM&A、すなわちホワイトM&Aの一般化という目標に向かわせる。
【プロフィール】
髙野 健二(たかの・けんじ)
株式会社M&Aコンサルティング 代表取締役
上場企業にてM&Aの交渉から調査、買収後の統合、子会社のマネジメントまで幅広い経験を積む。その後、M&A専業の公認会計士として10年以上開業。2016年に法人化し、株式会社M&Aコンサルティングを設立。
M&Aの実務経験と公認会計士としての専門知識を活かし、特に買収後の統合支援に強みを持つM&Aアドバイザーである。