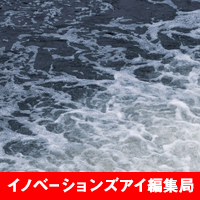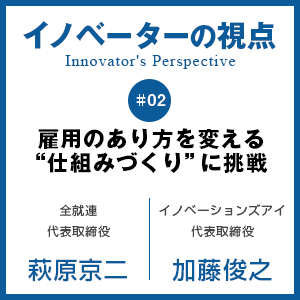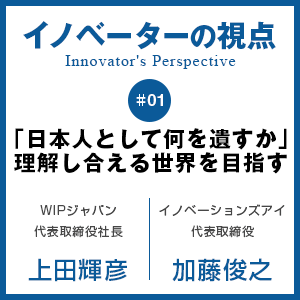再生スマホの普及を見据えニューズドテックが本格参入 循環経済に挑む

中古品を新品同様に修理・再生するリファービッシュがスマートフォンにも広がろうとしている。新品より安く、中古品より製品状態が良いうえ、環境にも優しいからだ。「温故知創でモバイルを次世代につなげる」を使命に掲げるニューズドテックは、モバイルを使い切る時代を見据え、リファービッシュ(再生)スマホのレンタル・販売事業に本格参入。独自で再生スマホの供給体制を整えたほか、ドバイに生産拠点をもつエコテックと提携し市場拡大に備える。「遅れている」といわれるスマホのサーキュラーエコノミー(循環経済)の実現に挑む。
リファービッシュ(Refurbish)とは「改修する」「磨き直す」という意味をもつ。初期不良品や故障などの理由で返品されたものをメーカー自身が修理し、新品と同じように使える状態にして再販売する。
故障の原因となった部品を交換し、動作確認を終えてから出荷されるのでユーザーは安心して購入できる。バッテリーも交換する。それでいて価格は新品より安い。新品スマホの価格が継続的に上昇する中、手ごろな価格を求めているユーザーにとって魅力的だ。
高品質かつ低価格なうえ、廃棄物や二酸化炭素の削減につながるため環境負荷が低い。環境意識の高まりとともに、再生スマホを選択するというサステナブルな消費行動の浸透が見込まれる。若い世代には中古品に対する抵抗意識が低いことも追い風だ。
さらに欧州で2024年2月に「修理する権利」の導入で合意。これにより、メーカーやメーカー公認の修理業者だけでなく、購入者自身が修理したり、自分で選んだ業者に修理を依頼したりすることが認められるようになった。EU加盟国は26年7月までに国内法を整備しなければならない。これにより第三者による修理・再生の動きが本格化すると見られている。
これを好機ととらえ、ニューズドテックは24年11月に、エコテックと業務委託契約を結んだ。25年を「スマホのリファービッシュ元年」とするためで、ニューズドテックは国内で買い取った中古スマホをエコテックに送り新品同様に再生して販売するほか、同社が独自に調達した中古を再生したスマホも国内で取り扱う。ともに「ニューズドフォン」の名称で25年初から販売すると好評で、特に新しいバッテリーに交換した再生スマホへの支持が高いという。
ニューズドテックの粟津浜一社長は「スマホを売って終わる時代から、スマホを使い切る時代にする。スマホをバトンのように何世代にもつなげる」と強調。仕入れた中古品を検品、データ消去、クリーニング、バッテリー交換、研磨により新品同様に再生して提供するという循環を繰り返すことで実現を目指す。これによりスマホの機能異常やバッテリー劣化などで「使えない」状態を防ぐとともに、再生スマホの認知度を高め、国内市場を創出する考えだ。
一方のエコテックは21年、アラブ首長国連邦(UAE)のドバイに設立。ドバイ空港のフリーゾーンに生産拠点を設けており、再生スマホを月間1万~1万5000台規模(能力は3万台)で生産する。端末を開けることなく外観を新品同様に再生できるほか、端末を開けてバッテリーなどの部品を交換する。現在はドバイから欧州やアフリカに出荷している。
25年にはアジア・北米向けの生産拠点として30%のコストダウンを実現したフィリピン工場(月産能力1万台、26年には5万台予定)を新設。さらに同年、日本にオフィスと工場を開設し、26年からの本格稼働に備える。修理・再生時間の短縮が可能になり、再生スマホの市場拡大につなげる考えだ。同社の木戸孝社長は「私のミッションは1億台といわれるタンス携帯をなくすこと。再生スマホが『市民権』を得ることで実現に近づく」と話した。
両者とも「再生スマホは盛り上がる」と口をそろえる。中古スマホを使いたくない理由として約4割が「品質とバッテリーに不安がある」を答えたアンケートもある。この課題を再生スマホが解決するからだ。スマホ業界に詳しい野村総合研究所の北俊一氏は「日本の中古スマホ市場は新品の約10%と世界で圧倒的に低い」と指摘。そのうえで「(中古スマホの普及には)健全な修理・再生市場の組成が欠かせない」と説く。「リファービッシュ元年」と位置付ける25年を契機に、新品か再生品かを選べる社会に近づくのは確かだ。