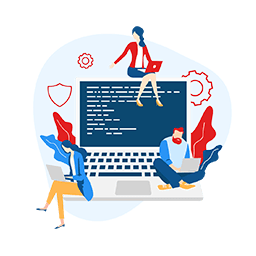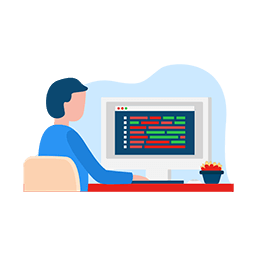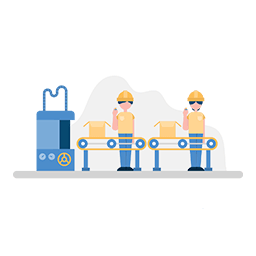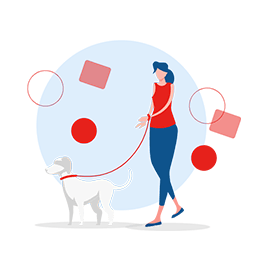あなたのビジネスを一歩先に進めるbizDB活用ガイド
決断の前に知っておきたい「廃業手続き」
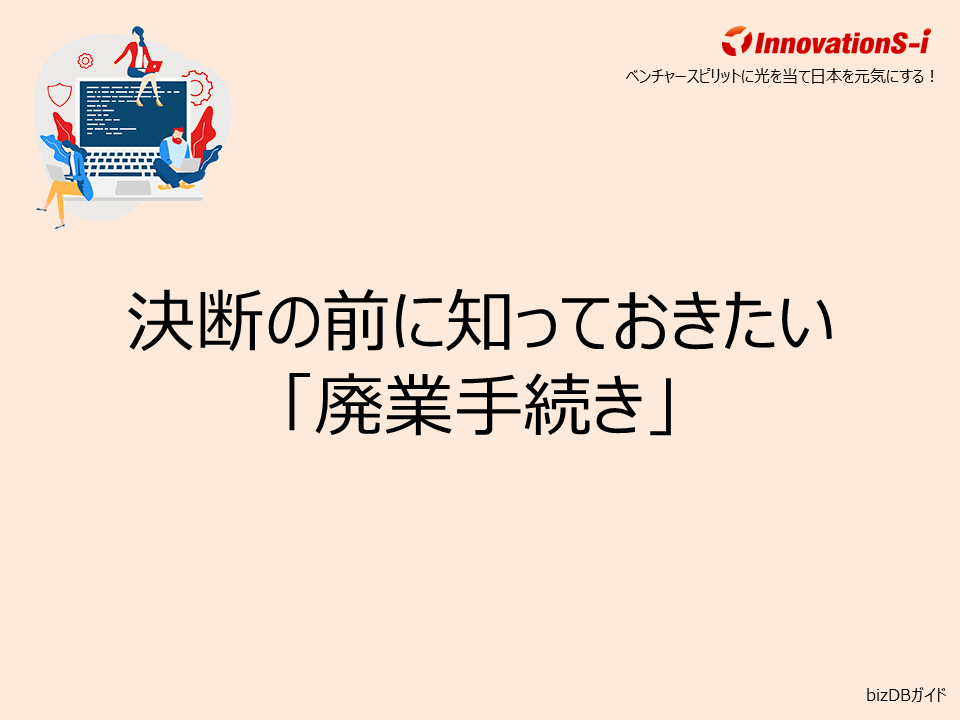
廃業とは? ~解散と清算の違い~
会社を廃業するには、次の2つのステップが必要です。
① 解散
「会社としての活動を終了する」ことを宣言。会社の営業活動を停止し、清算に入る。
② 精算
会社の財産を整理し、債務を返済したうえで残余財産を分配すること。手続き終了後に法人登記が抹消される。
※個人事業主の場合は「廃業届」の提出だけで済む場合もあります。
法人廃業の流れ(株式会社の場合)
以下は、一般的な株式会社の廃業(任意解散)の手順です。
① 株主総会の開催・解散の決議
・株主総会で「解散」と「清算人の選任」を決議(特別決議が必要)。
・株主が社長1人でも、議事録の作成は必要です。
② 解散登記・税務署等への届出
・法務局で「解散の登記」と「清算人の就任登記」を行う(2週間以内)。
・税務署、都道府県税事務所、市区町村へ「異動届」提出。
③ 債権者への公告・催告(最低2ヶ月)
・官報で「債権者は申し出てください」という公告を掲載。
・この間、原則として財産の分配は不可。
④ 財産の換価・債務の弁済
・残っている資産を売却し、負債をすべて精算。
・雇用契約の終了・未払給与の清算、社会保険・雇用保険の手続きなども含まれる。
⑤ 残余財産の分配(あれば)
・最後に残った財産を、出資比率に応じて分配。
⑥ 清算結了登記・法人の抹消
・清算報告書を作成し、株主の承認を得る。
・法務局で「清算結了登記」を行い、会社が正式に消滅。
廃業に伴う主な対応事項(社長がすべきこと)
●社員
雇用契約の終了通知、未払給与や退職金の支払い、離職票の発行、労働局・ハローワーク手続き
●取引先
契約解除・支払い調整・未回収債権の整理、信用不安を与えない説明の仕方も重要
●税務・社会保険
各種届出(法人税・消費税・源泉所得税、年金・健康保険)と最終申告
●金融機関・保証協会
借入金の返済・保証の解除、返済が困難な場合は早めに交渉
●在庫・固定資産
処分方法の検討(売却、廃棄)、資産台帳の整理
●代表者個人
廃業後の生活設計、年金、税金、健康保険、退職金・再就職の準備
廃業にかかる費用と期間の目安
解散・清算の登記費用:約4~6万円(登録免許税)
官報公告:約3.5万円/1回 × 2回(解散・清算)
税理士・司法書士報酬:10~30万円(自社でできる部分もあり)
清算期間:約3~6ヶ月(債権者の申し出期間があるため)
廃業以外の選択肢もある?
「廃業=会社をたたむ」ではありません。次のような選択肢も検討可能です。
●第三者へのM&A(事業譲渡・株式譲渡)
売上ゼロでも技術・取引先・人材などが“資産”として評価されることがあります。
●社内承継(親族・社員)
理解ある親族や社員がいる場合は、早めに相談することが大切です。
まとめ
廃業は、失敗ではなく、会社と社長の人生における「区切りの選択」です。重要なのは、「後悔のない終わり方」をすること。手続きを知り、社員や関係者に誠実に対応し、自分自身のこれからに向き合う。それが、経営者としての最後の大切な仕事です。もし迷いや不安があるなら、一人で抱えず、信頼できる専門家や支援機関に相談してみてください。
編集局の声
創業や挑戦が華やかに語られる一方で、「終わり方」について正面から語られる機会はあまり多くありません。でも私たちは、誠実な廃業には、次の挑戦につながる価値があると信じています。
M&A・事業承継カテゴリの商品・サービス
-
 M&Aは成立したけど、次のような悩み事はありませんか? ・M&A検討時に期待していたシナジーが出ない。 ・企業文化や経営体制を融合できない。 ・買収会社の業務が円滑に回らない。 ・買収会社をどのように管理していいか分からない。 ・業務プロ…資料請求・問い合わせできます
M&Aは成立したけど、次のような悩み事はありませんか? ・M&A検討時に期待していたシナジーが出ない。 ・企業文化や経営体制を融合できない。 ・買収会社の業務が円滑に回らない。 ・買収会社をどのように管理していいか分からない。 ・業務プロ…資料請求・問い合わせできます -
スタートアップの成長と事業会社の革新をつなぐアライアンス支援
株式会社Camphor Treeは、スタートアップと事業会社の双方に価値をもたらすアライアンス形成を総合的に支援しています。 共同研究開発、技術提携、販売提携、生産提携、M&Aアドバイザリーを通じて、スタートアップには成長・スケールアップの機会を、事業会社には外部の…資料請求・問い合わせできます -
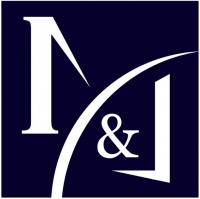 ◆相手先探し 弊社独自のネットワークを使用し、M&Aの相手先探しもいたします。 ◆M&A全般マネージメント M&Aの頭の先からしっぽの先までご相談をお引き受けするコンシェルジュとお考えください。 ◆バリュエーション(株価算定) M&A全般の知識と経験が…資料請求・問い合わせできます
◆相手先探し 弊社独自のネットワークを使用し、M&Aの相手先探しもいたします。 ◆M&A全般マネージメント M&Aの頭の先からしっぽの先までご相談をお引き受けするコンシェルジュとお考えください。 ◆バリュエーション(株価算定) M&A全般の知識と経験が…資料請求・問い合わせできます -
 スタートアップの事業成長や事業会社のオープンイノベーション戦略を実現するために、M&Aを活用した最適なパートナーシップ形成を支援します。スタートアップにとっては、技術・人材・プロダクトを次のステージへ進めるための資本・事業基盤の獲得を、事業会社にとっては…資料請求・問い合わせできます
スタートアップの事業成長や事業会社のオープンイノベーション戦略を実現するために、M&Aを活用した最適なパートナーシップ形成を支援します。スタートアップにとっては、技術・人材・プロダクトを次のステージへ進めるための資本・事業基盤の獲得を、事業会社にとっては…資料請求・問い合わせできます -
 M&Aの業者が強引に進めているように感じる M&A業者との契約が妥当なものかどうか疑問に感じる 付き合いのある税理士に相談したものの、経験がないため頼りなく感じる、あるいは保守的過ぎて現実的なアドバイスがもらえない M&Aは一生のうちに一度経験するか…資料請求・問い合わせできます
M&Aの業者が強引に進めているように感じる M&A業者との契約が妥当なものかどうか疑問に感じる 付き合いのある税理士に相談したものの、経験がないため頼りなく感じる、あるいは保守的過ぎて現実的なアドバイスがもらえない M&Aは一生のうちに一度経験するか…資料請求・問い合わせできます -
迅速かつ最適なワンストップの問題解決(ソリューション)を提供
当事務所では、通常法務について幅広く対応できる体制をご提供することはもちろん、それ以外にも、海外関連、知的財産戦略、M&A、ファイナンス、企業側に特化した労務、不祥事(事件・事故)対応といった、特殊性や専門性が高い分野についても、それぞれに高度に専門化し…資料請求・問い合わせできます -
中小企業のIPO・M&A、資金調達、並びに従業員の資産形成をサポートします!
【事業拡大サポート】 ◆M&A(買い) ◆ビジネスマッチング 【出口戦略サポート】 ◆事業承継(親族間、従業員、M&A) ◆税制適格ストックオプション管理 【IPOコンサルティングサポート】 ◆公開準備支援 ◆資本政策や企業評価、財務戦略等の提言…PDFカタログダウンロードできます 資料請求・問い合わせできます -
 それぞれ異なる文化、異なる環境を有する会社同士を統合していくことがPMIになりますので、答えはひとつではなく、それぞれの状況によって選択する進め方も変わっていきます。 しかしそこにも原理原則は存在しています。 弊社ではM&Aの相手探しだけではなく、M&A実…資料請求・問い合わせできます
それぞれ異なる文化、異なる環境を有する会社同士を統合していくことがPMIになりますので、答えはひとつではなく、それぞれの状況によって選択する進め方も変わっていきます。 しかしそこにも原理原則は存在しています。 弊社ではM&Aの相手探しだけではなく、M&A実…資料請求・問い合わせできます