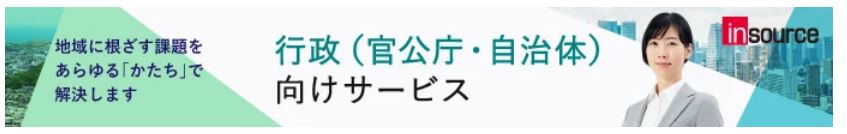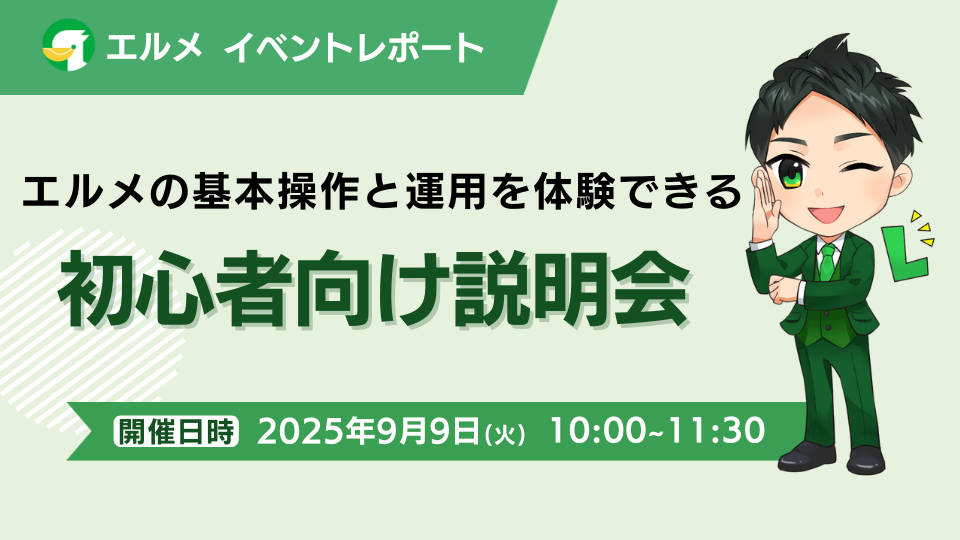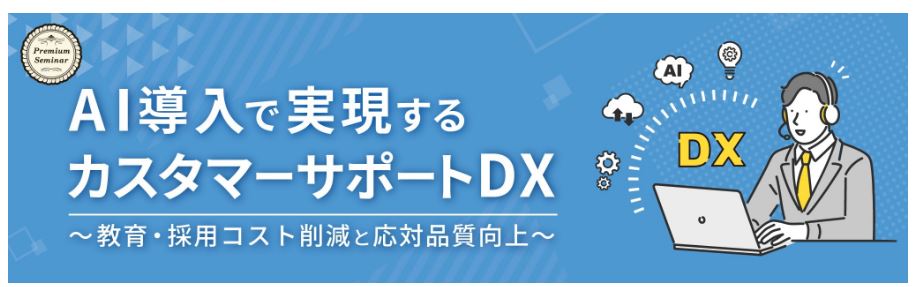■レポート概要
――――――
市場規模と成長見通し
掲載概要によれば、世界の水産飼料市場は2025年の421億米ドルから年平均成長率(CAGR)7.5%で拡大し、2032年末には699億米ドルに達する見通しです。成長の基調として、水産物消費の増加、養殖への関心の高まり、天然漁場の縮小に伴う持続可能なタンパク源へのシフトが明示されています。さらに、医薬品・食品飲料・栄養補助食品等の分野で有機魚油の需要が高まっていること、健康効果への認識の普及や慢性疾患増加にともなう魚介類摂取の拡大が、世界的な需要押し上げ要因として整理されています。
――――――
市場の定義と導入背景
レポート紹介では、マリンフィードを「水生動物の栄養ニーズを満たすために商業的に生産される飼料」と定義しています。主原料や添加物には、魚油、植物性タンパク質、海洋生物由来原料、穀物製品、陸上生物由来の生餌などが含まれ、タンパク質・脂質・ミネラル・ビタミン・炭水化物等を適切に配合して、成長・繁殖の効率化と健康維持を図ることが基本的な目的とされています。持続可能性と資源効率の観点から、従来資源の置換・補完としての役割が期待される点も、この市場が注目される背景に位置づけられています。
――――――
成長ドライバー
市場成長を下支えする具体要因として、(1)魚およびシーフードの消費増、(2)養殖の拡大、(3)環境配慮や気候変動対策の要請が挙げられています。紹介ページでは、魚が良質なタンパク質・オメガ3脂肪酸・ビタミン・ミネラルの供給源であることが広く認識され、健康志向や環境配慮型のタンパク選好が強まった結果、食の側面からも需要が拡大していると説明されています。また、輸送・流通の発達により消費者接点が広がったことも需要拡大に寄与しています。
――――――
抑制要因
一方、環境と公衆衛生への懸念が市場拡大のブレーキとなる可能性がある点が明示されています。集約的な養殖は周辺水域での栄養塩濃度上昇(富栄養化)や未摂餌・排泄物による水質悪化を招き得るほか、沿岸・湿地の改変に伴う生息地喪失、海草藻場・サンゴ礁・マングローブ等の脆弱な生態系への影響が指摘されています。こうした環境影響に対する社会的関心の高まりは、規制強化やサプライチェーンの負荷増につながるリスクとして認識されています。
――――――
市場機会
機会領域として「水産養殖に対する政府支援の増加」が挙げられています。紹介文では、各国政府が能力開発・教育プログラム、最良実践の普及、利害関係者間の知識共有などを通じて産業基盤の強化を後押ししている事例が示され、これらの施策が飼料需要の底上げに波及する構図が説明されています。国際機関の関与や戦略策定の取り組みも、市場の制度面での追い風として言及されています。
――――――
アナリストの見解
中流層の拡大と健康志向の浸透が水産物需要を押し上げるなか、養殖活動の拡大に伴って「高品質な養殖用飼料」への需要が増勢であるとの見解が掲載されています。経済的かつ栄養価に優れた配合技術の進歩が市場を牽引し、環境配慮型の手法への意識の高まりは「有機的で環境にやさしい飼料」開発の余地を広げるとまとめられています。
――――――
供給サイドの動向
サプライヤーは「持続可能性への貢献」と「正確な栄養設計」を両立させる役割を担い、今後5年間で新原料の活用、データ駆動の配合、先端技術導入により状況が大きく変化すると展望されています。環境に配慮した調達や責任ある水産養殖の採用が進むことで、持続可能性目標への整合が一層進むと記載されています。
――――――
セグメンテーション(主要区分と特徴)
対象種別(例示):魚類カテゴリーが2022年時点で最大のシェアを占め、栄養密度の高さと幅広い適用性から引き続き主導的と整理されています。軟体動物は予測期間中に高い成長率が見込まれる区分として挙げられ、二枚貝の生産拡大が背景と説明されています。
原料別:大豆ミールが2022年に優位であり、入手容易性と高タンパク性が普及を後押しすると記載されています。小麦・トウモロコシも、持続可能な代替原料の必要性を背景に拡大が見込まれると整理されています。
形状別:ペレットが取り扱い・保管・流通の利便性から主流で、漏出・ロスの低減、栄養安定や保存性、現場運用の実用性が評価されています。併せて、粉末(魚粉を含む)形状の割合も、栄養設計や加工技術の進展を背景に拡大が見込まれる旨が記されています。
流通チャネル:B2Bが主流で、養殖業の特性上、種別ごとのニーズに合わせた配合のカスタマイズが行いやすいことが理由として挙げられています。他方、責任ある調達・品質・安全に対する関心の高まりを受け、B2Cも意識の向上とともに一定の拡大余地が示されています。
――――――
地域別の概況
「北米が世界市場で優位を維持」と整理され、同地域の大規模養殖場の存在、魚介類需要の高さ、都市化・所得増・人口増の三要因が拡大ドライバーとして言及されています。また「東アジアは著しい成長が見込まれる」地域として示され、東太平洋における養殖の拡大と、それに伴う高品質飼料需要の増加が強調されています。中国の養殖サプライチェーンにおける飼料販売の重要性にも触れられ、地域の成長寄与が示されています。
――――――
競争環境と最近の動向
競争環境は、カーギル、アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド(ADM)、オールテック、バイオマール、ヌトレコなどグローバル大手に加え、環境配慮型やニッチ領域に強みを持つ地域サプライヤーが混在する複雑な構図と説明されています。研究開発、垂直統合、政府・学術機関との関与、スタートアップの台頭などが市場動態の変化要因として挙げられています。最近の主な動向として、2023年3月のADMによる海水魚の初期成長に特化したプレミアム飼料の投入、2022年5月のMSDアニマルヘルスによるDNA TRACEBACK Fisheriesプラットフォーム発表が紹介され、製品高度化やトレーサビリティの強化が市場に影響を与え得る事例として記載されています。
――――――
目次構成の骨子
紹介ページの章立ては、「レポート概要/市場成長の推進要因/市場の抑制要因/機会/アナリストの見解/供給サイドの力学/市場区分(対象種別・原料・形状・流通チャネル等のQ&A形式による要点整理)/地域別市場トップ/競争力のある情報とビジネス戦略/最近の主な動向」といった流れで、予測値・セグメント別着眼点・地域の注目点・主要プレイヤーと戦略・新製品や技術動向を俯瞰できる構成になっています。
――――――
まとめ
世界の水産飼料市場が「持続可能性と栄養の両立」を軸に拡大基調にあり、2025~2032年のCAGR7.5%で699億米ドルへ到達する展望を示しています。需要側では健康志向と水産物消費の拡大、供給側では正確な栄養設計・新原料・先端技術の導入が進展し、環境・公衆衛生リスクの管理と並走する形で市場が成熟していくシナリオが提示されています。セグメント面では、魚類・ペレット・大豆ミール・B2B流通が中核となり、地域面では北米の優位と東アジアの高成長が強調されています。競争環境はグローバル大手と地域プレイヤー、新興企業が交錯し、製品・トレーサビリティ・持続可能性を巡るイノベーションが今後の差別化軸となるでしょう。
■目次
――――――
2. レポート概要
・世界の水産飼料市場の成長見通し:2025年421億米ドル→2032年699億米ドル、年平均成長率7.5%
・市場機会の俯瞰(需要増・供給体制・規模化の視点)
・本レポートの構成と読み方(章立て・セグメント別分析・地域別比較)
――――――
3. 市場の紹介と定義
・水産飼料(マリンフィード)の定義・基本概念
・主原料と添加物(魚油・植物性タンパク質・海洋生物・穀物由来・陸上生物由来の生餌 等)
・栄養素の役割(タンパク質・脂質・ミネラル・ビタミン・炭水化物)と成長・繁殖への寄与
・水産養殖における機能・位置づけ(健康維持・飼育効率・品質)
――――――
4. 市場成長の推進要因
・魚介類の消費増加(健康志向の高まり・栄養価への認知・輸送/流通の発達)
・養殖拡大と持続可能なたんぱく源へのシフト(天然漁場の枯渇・環境配慮の高まり)
・有機魚油需要の拡大(医薬・食品・栄養補助食品など多用途での利用)
・気候・サステナビリティ観点での優位性(資源効率・排出削減の期待)
・広がる用途別需要と市場拡大の連動
――――――
5. 市場の抑制要因
・環境・公衆衛生への懸念(水質汚染・富栄養化・酸素欠乏・生息地改変)
・未摂餌飼料・排泄物による周辺環境への影響
・沿岸・湿地・藻場・サンゴ礁・マングローブなど繊細な生態系へのリスク
・発展途上国における近代的給餌技術の知識不足(旧式手法の残存・生産性低下)
――――――
6. 市場機会
・各国政府による水産養殖支援(政策・資金・人材育成)
・能力開発・教育プログラム(研修・ワークショップ・最良慣行の普及)
・国際機関・地域連携による戦略策定・対話促進(例:国家水産養殖開発戦略)
・新原料・データ駆動型配合・先端技術導入による製品・生産性向上
――――――
7. アナリストの見解
・中間層拡大・健康志向の強まりが生む需要押上げ
・高品質な養殖用飼料需要の増加とメーカーへの期待
・環境配慮・有機的で持続可能な飼料開発の可能性
・技術発展(経済性・栄養価・環境性)の波及効果
――――――
8. 供給サイドの力学
・サプライヤーの役割(栄養要件に最適化した設計・持続可能性への貢献)
・新原料・データ連携・最先端技術導入による構造転換(今後5年の展望)
・正確な栄養設計・責任ある調達・持続可能な養殖実践の広がり
――――――
9. 市場区分(セグメンテーション)
9.1 製品種類別(例:魚類/甲殻類/軟体動物 など、用途特性に応じた構成)
・魚類カテゴリー:2022年における支配的区分(高栄養・汎用性)
・軟体動物カテゴリー:予測期間中の高成長見込み(二枚貝需要 等)
9.2 原料・成分別
・大豆ミール:2022年の優位性(入手容易性・高タンパク・安定供給)
・小麦・トウモロコシ:代替原料・持続可能性志向に伴う拡大見通し
・その他:魚油・植物性タンパク・海洋生物由来原料 等
9.3 形状・製品形態別
・ペレット:養殖現場での重要性とシェア拡大見込み
・その他形態:運用・対象種に応じた使い分けの整理
9.4 エンドユーザー別
・水産養殖(魚類・甲殻類・軟体動物 等の飼養用途)
・畜養・研究・その他用途(該当する場合の位置づけ)
9.5 地域別
・北米/欧州/アジア太平洋/ラテンアメリカ/中東・アフリカの比較枠組み
・規模・成長率・政策・サプライ/需要特性の整理
――――――
10. 市場規模と予測(価値ベース)
・総市場:2019年~直近期の整理、2025年推計、2032年予測(CAGR 7.5%)
・製品種類別の市場規模・予測(主要カテゴリーの寄与度を含む)
・原料・成分別の市場規模・予測(大豆ミール・穀物類・その他)
・形状・製品形態別の市場規模・予測(ペレット他)
・エンドユーザー別の市場規模・予測(用途に応じた需要プロファイル)
・地域別の市場規模・予測(各地域の成長要因・抑制要因の要点)
・基準/上振れ/下振れシナリオの比較(前提条件の整理)
――――――
11. 規制・環境・サステナビリティ
・環境影響・公衆衛生リスク管理(水質・生態系保全・排出)
・持続可能な調達・配合・製造の実践(循環性・トレーサビリティ)
・政策・支援策の最新動向(支援プログラム・国際連携の枠組み)
――――――
12. 技術・イノベーション動向
・データ駆動型配合・最適化(成長・餌料効率・コスト最適)
・新規原料の探索と評価(植物・微生物・副産物活用 等)
・生産・供給チェーンでの自動化・標準化(品質・安定供給)
――――――
13. 需要サイドの洞察
・健康志向・栄養認知の高まりと消費パターンの変化
・流通・アクセス性の改善(輸送・保管・コールドチェーン)
・価格感応度・品質要求・安全性への期待
――――――
14. 供給チェーン・流通
・原料調達~製造~出荷~最終用途までの流れ
・地域・用途に応じた供給網と在庫・品質管理
・協業・知識共有による効率化とレジリエンス強化
――――――
15. 競争環境(概観)
・プレイヤーのポジショニング(原料・配合・技術の差異化)
・提携・投資・研究開発の動向(生産能力・品質・コストの高度化)
・地域戦略と市場参入・拡大の要点
――――――
16. 図表・付録
・主要図表一覧(市場規模推移/セグメント構成/地域比較/サプライチェーン模式図 等)
・用語集・定義の再掲(製品種類・原料・形状・用途)
・調査前提・データソース・注記
■レポートの詳細内容・販売サイト
https://www.marketresearch.co.jp/marine-feed-market/