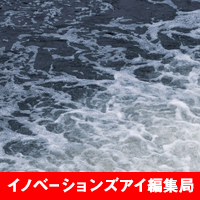FTI JAPAN 鳴海健太朗社長
インドネシアを中心に天然マグロの輸入販売を手がけるFTI JAPANは、現地出荷体制の整備に伴う品質の安定化などで販売ルートを拡大、昨年10月には単月黒字化を達成。これを機に、今月から新たな取引ルートとしてBtoBのネット通販にも乗り出した。これにより月間10トン規模の販売量を年内に50トン規模に引き上げる。鳴海健太朗社長は「ロジスティクスと漁業権取得といったビジネスのプラットホームを固めたので、輸入販売する魚種の拡大などで攻めていく」と今後の展開に意欲を見せる。
--昨年11月開催の「革新ビジネスアワード」でファイナリストに選ばれた
「アワードでは、経営理念である『おいしいマグロを毎日の食卓に低価格で提供する』ためのビジネスプランを紹介した。それ以来、いろいろなところから声がかかるようになった。企業ビデオも制作し、認知度向上に努めている。川崎市の『かわさき起業家オーディション』にも応募する予定で、これからが楽しみだ」
--インドネシアでの事業内容は
「インドネシア政府と適正なパートナーシップを組むことにより、リーズナブルで高品質な海産物を日本に届ける事業基盤を確立することができた。事業エリアは、インドネシアでも資源量が豊富なバンダ海・セラム海に囲まれるマルク州西セラム県。日本の食卓に並ぶボリュームゾーンの大衆マグロであるキハダマグロやメバチマグロを収穫し空輸で輸入販売している。この海域は熱帯なので、季節ごとの収穫量や品質にばらつきがなく評価も高い」
--取りすぎによる天然マグロの枯渇の心配は
「この海域の資源状況を見ると、潜在資源量に対する生産量つまり利用割合はバンダ海が28%、セラム海は35%。インドネシア合計が63%なので漁獲量は少ない。われわれは年間3万5000トンの漁獲枠を持っているが、ロジスティクスの問題から現状は120トンにとどまっており、インドネシア政府から『もっと取っていい』といわれている」
--それだけ政府から期待されている
「首都ジャカルタやスラバヤなど工業を中心に発展を遂げる都心部とは対照的に沿岸部は開発が遅れており、貧困層が多く失業率も高い。このためジョコ政権は海洋資源開発を優先政策に掲げており、われわれはインドネシアに漁業技術や鮮度保持技術を導入し、水産業の効率化と安定漁獲、海産物の高品質・高付加価値化で貢献したい。われわれが輸入するマグロを日本人がおいしく食べることで、インドネシアの貧しい漁村で暮らす人々の生活向上につながる。生産者が買いたたかれることもなく、フェアトレードを実現できる」
--今後の展開は
「天然マグロの輸入量を増やしていくが、一方で魚種も拡大していく。赤魚やマナガツオ、オニアジ、ハタ、オニエビなどインドネシアの水産資源を今年から日本に入れたい。ブランド化もできる。全魚種で3~5年後には3万トンの輸入販売を目指す。おいしいので日本とインドネシアの両国にとって国益にかなう。また空港の施設などロジスティクスの拡充にも取り組んでいく」
【プロフィル】
鳴海健太朗 なるみ・けんたろう
東京薬科大薬学部卒。2004年日本ベーリンガーインゲルハイム(現ベーリンガーインゲルハイムジャパン)入社。リジョイス、国際ライフサイエンスを経て12年FTI JAPAN入社。13年10月から社長。35歳。新潟県出身。
【会社概要】
FTI JAPAN
▽本社=東京都千代田区内神田2-4-2 IK内神田ビル301号
▽資本金=6000万円
▽設立=2010年7月
▽社員=9人
▽事業内容=天然マグロなどの輸入販売事業
「フジサンケイビジネスアイ」